From 青木泰樹@経済学者
——————————————————-
●世界を動かす力の正体とは?
『激流グローバルマネー』のフルバージョンが聞けるのは3/10まで
https://www.youtube.com/watch?v=xSpcGUoATYk&feature=youtu.be
※※月刊三橋『激流グローバルマネー』より
——————————————————-
あちらを立てれば、こちらが立たず。
物事の両立というのは、なかなか難しいものです。人間関係もまた然り。
こうした状況を経済学ではトレード・オフ(trade-off)と呼びます。
最も有名なのは、失業率とインフレ率の逆相関関係を示す「物価版フィリップス曲線」でしょう。
リフレ派の重鎮である浜田宏一内閣官房参与は、常々、リフレ政策によって雇用増へ至る理論的経路を著作や雑誌等で説明しておりますが、それを見るたび先の言葉が頭をよぎります。
今回は、リフレ派の論理における「雇用量と実質賃金(率)のトレード・オフ」についてお話します。
また、その論理に従えば、リフレ政策によって雇用量が増えることはあっても実質賃金は上がらないことを示します。
リフレ政策は二段ロケットに似た構造をしています。
一段目は自力ロケットで、「人々の期待(予想)を変える」ところまで運ぶのが役割です。
具体的には、日銀が2%のインフレ目標を掲げ、それを達成するまで量的緩和を続けるとコミットメント(公約)することによって人々のインフレ期待を高めるという政策手段です。
二段目は他力ロケットで、「期待を変化させた人々が、リフレ派の思惑通りの経済行動をとる」ところまで運ぶのが役割です。
しかし、自由主義経済である以上、不確実性下にある現実経済において如何なる経済行動をとるかは個人や企業に委ねられております。
リフレ派が幾ら「経済学の教科書通りの行動をせよ」と力んだところで強制はできません(さらにリフレ派は相反する諸学説を継ぎはぎしたような論理構造なので、状況に応じて適宜教科書を使い分けているように思われます)。
完全に他力なのです。二段目のロケットはどこへ飛んで行くかわからないのです。
リフレ政策が壮大なる実験だとよく言われるのはそのためです。
リフレ派にできることは、唯一つ、個人や企業が自分たちの思惑通りの行動をとることを願い、そしてそれを念じることだけなのです。
今回の話題は、正に教科書経済学と現実経済の動向の齟齬に関するものです。
リフレ政策を二段ロケットと考えると、その成否は一段目だけでは問えません。
確率はかなり低いでしょうが、仮に一段目が成功したとしても、それだけでは不十分なのです。
2%のインフレ率の定着によって実体経済、すなわち人々の暮らし向きが良くならなければ、何の意味もないのです。
言うまでもなく、人々の暮らし向きは実質賃金の動向に左右されます。
名目賃金の上昇率がインフレ率を上回れば実質賃金は上昇し、逆は逆ということです。
それではリフレ政策によって名目賃金はインフレ率以上に上昇するのでしょうか。
浜田宏一氏は、予想インフレ率が上昇した場合、将来の実質賃金が下落するため企業は雇用を増やすと論じています。
これは新古典派の教科書に載っている企業の利潤最大化行動の理論に基づく話です。
時折、ケインズも『一般理論』において古典派の第一公準(労働需要の理論)を否定していないのだから、労働需要の考え方は新古典派と同じであると考える学者もおります。
ケインズ経済学を均衡論的枠組みに押し込めた「IS−LM分析」に立脚していたアメリカ・ケインジアン(現在はオールド・ケインジアンと呼ばれています)の系譜に連なる考え方です。
しかし、それはケインズ経済学のほんの一面しか見ない浅薄な理解といえます。
資本主義経済の不安定性の根源としての不確実性の存在、さらに貨幣愛および「アニマル・スピリット(血気)」といった非合理な動機に基づく経済行動を重視したケインズ経済学の全体像を見失っては、本質的理解には程遠いと言わざるを得ません。
さて、話を進めましょう。
企業が雇用を増やした時、循環的失業者(一般にリフレ派は非自発的失業者とは言いません)がいれば、彼等が全員雇用されるまで名目賃金は上がらないが、失業率は改善するとリフレ派は論じています。
すなわち完全雇用に至るまで実質賃金は上がらないばかりか、インフレ率の上昇分だけ下がるということです。
さらにリフレ派は「完全雇用状態に達して、尚、労働需要の超過があれば、はじめて名目賃金は上がり始める」と続けます。
しかし、完全雇用状態において労働に対する超過需要が存在するという想定は新古典派にはありません。
労働の需給一致点で均衡実質賃金率が決定され、その際の雇用量が完全雇用水準です。そこから離脱する誘因は新古典派の世界において内生的には存在しません。
利潤最大化が達成されている状態から離れたがる企業はいないからです。一番幸せな状態を捨てたい人がいないのと同じです。
したがって、その想定はリフレ派独自のものでしょう。
今度は、労働需給が新古典派のように必ずしも一致しない状況を想定できるケインズ的な労働市場の登場です。
さて、名目賃金が上がりだしたとして、上昇幅はインフレ率を超えるのでしょうか。
超えれば実質賃金が上昇しますので、2%のインフレ下においても人々の暮らし向きは改善します。
しかし、残念ながらそうはなりません。
企業にとって名目賃金の上昇は、予想インフレ率一定の下では予想実質賃金の上昇を意味しますから、その新たな実質賃金の下で最適化(利潤最大化)を図るために、今度は雇用量を減少させねばなりません。
そうして決定された最適雇用量が完全雇用以下である場合には、名目賃金は上がりませんから実質賃金も永遠に上昇しません。
それでは最適雇用量が完全雇用以上である場合は、どうでしょうか。
確かに、この場合、名目賃金は上昇するでしょう。
しかし、同時にそれは実質賃金の上昇を意味しますから、再び最適雇用量は減少しなければなりません。
その新たな最適雇用量が依然として完全雇用以上である場合、名目賃金は上昇しますが再び実質賃金も上昇しますので、さらに最適雇用量は減少します。
この過程が続くとどうなるのでしょう。
結局、最適雇用量と完全雇用が一致するところで落ち着くでしょう。
さて、その場合の名目賃金は、当初と比べて2%以上上昇しているでしょうか。
残念ですが、このケースもそうはなりません。
名目賃金は2%上昇するのが精一杯なのです。
リフレ派は、予想インフレ率が2%に高まることで将来の実質賃金が下がり雇用が増えると考えています。
しかし、生産技術を一定と仮定したとき、もしも名目賃金が2%上昇すると実質賃金はインフレ予想が高まる前の水準に戻ってしまいます。
それは結局、雇用量が元の水準にまで減少することを意味します。
リフレ政策をする前に戻るのです。
元の水準が完全雇用以下であれば、リフレ政策をしてもしなくとも同じことになります。
人々の暮らし向きも同じ水準です。
もしも最適雇用量が完全雇用水準にとどまるとしたならば、実質賃金はリフレ政策発動前よりも低くなければなりません。
すなわち名目賃金の上昇は2%以下でなければならないのです。
以上より明らかなように、リフレ派の理屈に従えば、「リフレ政策によって実質賃金は下落する」と結論づけられるのです。
すなわちリフレ政策を実施すると人々の暮らし向きは悪化することになってしまいます。
一言で言えば、リフレ政策は「雇用量と実質賃金のトレード・オフ関係」に立脚したものであり、リフレ派の理屈からは雇用増と実質賃金上昇という二兎を追うことはできないのです。
その論理構造は、新古典派の雇用量と実質賃金の関係を、ケインズ的な労働市場に当てはめているに過ぎません。
リフレ派は人々の期待を変えれば実物的要因(今回の場合は雇用量)に影響を及ぼすことが可能であると論じています。
しかし、その対象とする「人々」が新古典派およびその後継の学説である「新しい古典派」の想定する合理的経済人の場合、リフレ派の論理は通じません。
特に、最新の経済モデルや統計データに基づいて合理的期待を形成する「超」合理的経済人には全く歯が立ちません。
これまで見てきたように、リフレ政策が雇用増につながるのは、「2%の予想インフレ率に名目賃金の上昇率が追い付かない」ケースだけなのです。
それも人々の暮らし向きを悪くすることで(実質賃金を引き下げる)、雇用増が図られたのです。
経済学の用語を用いれば、経済主体が貨幣錯覚を起こした場合にだけ短期的に成立する現象なのです。
それゆえ貨幣錯覚を起こさない合理的経済人には通じないのです。
なぜなら合理的経済人は貨幣の中立性を前提とする経済モデルに立脚し、「2%の予想インフレ率とは将来の2%の名目賃金上昇率を意味する」と即座に見抜くため雇用量を変化させないからです。
もっとも私は、リフレ派にも新しい古典派にも与するものではありません。
現実経済において、企業経営者が限界原理に基づく論理に従って、実質賃金の水準を見て雇用量を決定するとは考えられないからです。
そこには既存の経済学とは別の論理が必要となるでしょうが、それは別の機会に譲ります。
さて、リフレ政策は、彼等の理屈に基づくと、単独では実質賃金を上げられないことがお判り頂けたかと思います。
それゆえ実質賃金を引き上げるためには、他の政策手段が必要になってくるのです。
安倍政権下で実施されている政労使間の協議における賃上げ交渉であるとか、効果は甚だ疑問ですが、労働生産性を向上させるとする成長戦略に頼らざるを得ないのです。
しかし、成長戦略との邂逅は問題です。
結局、リフレ派は新自由主義的政策を指向する経済学者達、いわばネオリベ経済学派と歩調を合わせて行進してゆくと思われますから、日本経済の将来にとって心配の種は尽きません。
PS
もしあなたが日本経済の行く末がご心配でしたら、、、、
「日本を救う方法」をいっしょに考えませんか?
http://www.keieikagakupub.com/sp/CPK_38NEWS_C_D_1980/index_sv2.php












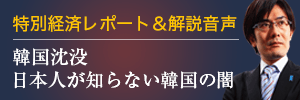
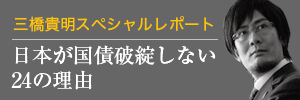



【青木泰樹】教科書経済学と現実のズレへの2件のコメント
2015年3月8日 2:41 PM
シュレーディンガーの猫をご存知ですか?現実は生き物です。それをある瞬間だけ過去に切り取った記録だけ見ても未来には全く別の様相を見せる可能性が常にある。人の生産物なら出来うる限りの試行錯誤を行い帰納的に法則を見出しその生産物を理解し、安全性をある程度は保障できますが、この世界は人が創ったわけではない人智を超えた存在です。それが僅か数千年の文明による記録の結果簡単にわかるという発想がはなから間違いですね。初めに書はなく、ミネルバの梟は黄昏に飛び立つのです。学問は常に現実の後追いですよ。どちらにしてもです、地球上に人が余っているという認識の下に人を余剰資源と見て生産のための消費物とみなす行為は肯定されるべきではありません。そのような考えは非文明的であり、文明を維持発展させるどころか、いずれ文明を滅ぼすに至るでしょう。死を称賛する為の文明はありえません、文明は生を肯定し称賛するものです。善く生きるための文明であります。全ての事は我々の無知さから来ることなのですから、無知である事で開き直ったら人間はお終いです。そういう連中を悪魔と言いますね。人は神ではないのだから絶えず真理を希求せねばなりません。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2015年3月9日 5:01 AM
信ずるものは自死をみろ!リフレにしろネオリベにしろ悪魔の囁きのごとき諸説を心底信奉できるその精神構造に僕はとても興味がありますが、、、彼等の知的好奇心を満たすために国民が実験用動物に供されている事態には強い憤りをおぼえます。経済政策という名の人体実験は赦されるものなのでしょうか?実験失敗により何万もの国民が自死においやられる悲劇を看過できる精神構造とはいったいどういうものなのでしょうか?人間の首から上はいまだに中世の闇に覆われているのかも知れませんね。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
コメントを残す
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です