From 施 光恒(せ・てるひさ)@九州大学
———————————————
【PR】
日本が途上国支援を続けられる訳
消費増税、高齢化、千兆円の政府債務
借金大国の日本が世界貢献できる訳とは・・・
http://www.keieikagakupub.com/sp/38DEBT/index_mag1.php
———————————————
おっはようございま〜す(^_^)/
このメルマガが配信されるころには、英国のEU離脱の是非を決める国民投票、もう大勢が明らかになりつつあるころだと思います。
国民投票の結果がどうなるかわかりませんが、加盟国がEUを離脱しようという動きは、今回の英国がどちらを選択するとしても、今後、たびたび生じるでしょう。
数日前にも、イタリアのローマ市長選で、EU懐疑派の新興政党「五つ星運動」の候補ビルジニア・ラッジ氏の当選が決まりましたし。
日本の評論家やマスコミは、「EUは人権や民主主義の理念を体現したものだ」といった具合に好意的にみる場合が多いですが、EU自体に民主的正当性があるかどうかは、実は結構、疑問です。EU加盟各国の人々の多くが、本当にEUを支持しているとはなかなか言い難いのです。
例えば、2004年から2005年にかけて、EUのいっそうの政治的統合を進めるために「欧州憲法条約」(EU憲法条約)を制定しようという動きがありました。欧州憲法条約の発効には、全加盟国の批准が必要でした。批准の是非を決める手続きは国によって異なり、議会承認だけで済ます国と、国民投票を行う国とがありました。
フランスやオランダ、イギリスなどは、国民投票が必要な国でした。それで、フランスは2005年の5月末に、オランダは6月に、それぞれ国民投票を行ったのですが、どちらの国でも、否決されてしまいます。つまり両国では、EU統合推進を否定する側が勝ったのです。
そのため、イギリスやアイルランドなどその後に国民投票が予定されていた国も、実施を延期してしまいました。それで結局、欧州憲法条約は立ち消えとなります。
その後、しばらく冷却期間を置いたのち、2007年には、欧州憲法条約をよりマイルドにし、統合推進の色彩を薄めた「リスボン条約」(EU基本条約)の批准手続きがはじまりました。
欧州憲法条約の二の舞となることを恐れた各国政府は、リスボン条約の批准に際しては、国民投票を回避し、議会承認で済まそうとします。ただ、アイルランドだけは、自国の憲法での取り決めとの関連で、国民投票を回避することはできませんでした。
そのため、2008年6月に国民投票を実施したのですが、ここでも、リスボン条約反対派が、つまりEU懐疑派が勝ってしまいました。
欧州憲法条約やリスボン条約の国民投票の結果から推測されるように、加盟各国で国民投票をすると、EU懐疑派が勝つ可能性は決して少なくありません。
その意味で、EUに民主的正当性があるかどうかは怪しいのです。
EU懐疑派の懸念は、一つは、EUはどうしても新自由主義的政策を推し進めがちで、「勝ち組」に有利な政策が増え、庶民には厳しい政治が常態化してしまうのではないかという点です。
例えば、欧州憲法条約がフランスで否決された際、ある記事は次のように伝えていました。
***
EU憲法、グローバル化の勝ち組は賛成? パリで80%超える区も
(『朝日新聞』東京本社版2005年5月31日夕刊)
欧州連合(EU)憲法条約を拒絶したフランスの国民投票で、パリの商業地や高級住宅地での賛成率が80%前後に達したことが分かった。反対派が「自由競争に偏りすぎ」と批判するEU憲法を、欧州統合を前向きにとらえる「グローバル化の勝者」が懸命に支えようとした様子が浮かび上がる。
内務省によると、全国で賛成45%という結果に対し、大都市の賛成率はパリ66%、ストラスブール63%、リヨン61%と総じて高い。地中海の「移民の街」マルセイユは例外で、大幅に低い39%だった。(以下、略)
***
フランスの歴史人口学者エマニュエル・トッドも、次のようにEUの新自由主義的性格を批判しています。
***
ブラッセルにある欧州委員会のメンバー選出は、選挙によらない極めて不透明なもので、「ブラッセル体制」とは、ヨーロッパの政治エリート同士の談合による寡占を表現したものと言えます。
そしてナショナルレベルの政治リーダーは、不人気な政治政策を実行するときは、「いや、これは欧州委員会で、EUレベルで決まったことだから受け入れざるを得ないんだ」と、上から押し付ける形で、例えば自由化や民営化のような大衆には不人気な政策を実行する。
こうした二重構造がある以上、少なくともEUに関しては、「デモクラシー以後」という事態がすでに始まっていると言わなければなりません。
(E・トッド/石崎春己編『自由貿易は、民主主義を滅ぼす』藤原書店、2010年、39頁)。
***
EUは確かに、加盟各国を「統合」しますが、その反面、EUの内部では、グローバル化した経済のなかで利益をえられる少数の「エリート」と、緊縮財政や福祉の削減、移民流入に伴う人件費の低下などの悪影響を被る各国の「庶民」という「分断」が生じます。
EUをめぐるこのような「統合」と「分断」という点に関しては、少々古いですが、もう一つ、興味深い記事があります。2008年6月のアイルランドの国民投票でのリスボン条約否決直後の首都ダブリンの様子を伝えるものです。
***
「EU基本条約否決 小国の反乱 統合に打撃」
(『朝日新聞』2008年6月15日付朝刊)
13日夜、開票結果が発表されたダブリン市内の会場。不思議な光景だった。
中絶反対を訴える宗教右派の団体の横に左翼グループ、後ろには民族主義のシンフェイン党支持者。近くのホテルでは企業家グループが勝利会見を開いていた。条約批准に反対し続けてきたのは、何の共通点もない人々だった。
(中略)
また、反対票を投じた人々からは「仏独など大国主導のEUには反対」「われわれが選んだわけでもないブリュッセル(EU本部所在地)のエリート官僚がすべてを決めてしまう」との声も上がっていた。(以下略)
***
上記の新聞記事では、捉え損なっていますが、ダブリンで条約批准に反対し続けた人々は、「何の共通点もない人々」ではありません。これらの人々には、「アイルランド人」という共通点があります。私は、このことはとても大切だと思います。
普段あまり意識されませんが、ナショナリティ(国民意識)という絆が重要なのは、ここに表れているように、「宗教右派」、「左翼」、「民族主義者」、「企業家」といった多様な信条や利害を持つ人々をまとめる力を持つという点です。
一般に、人は、自分と信条や趣味、利害が近い他者とは、協力しあうことが可能ですが、これらを異にする他者とは、なかなか協力しあったり、連帯したりできません。ナショナリティという絆は、少々不思議ですが、イデオロギーや利害、趣味、社会的経済的立場が大きく違う者同士の長期間にわたる協力や連帯、相互扶助を可能にするのです。
あらためて考えてみれば自明ですが、いまにいたるまで、自由民主主義の政治は、「国民国家」という単位でしか実現していません。つまり、「平等」(再分配的福祉)や「民主主義」を重視する政治は、ナショナリティという絆なしではおそらく成り立たないのです。「同じ国民だから」という意識がないところでは、経済的立場や思想・信条を大きく異にする者同士が(たとえいやいやながらであっても)連帯したり、助け合ったりしていくことは実際上、大変困難なのです。
ヨーロッパは、他の地域と比べれば、歴史的にも宗教的にも同質性が高く、「EU人」とでもいうべきトランスナショナルな(超国家的な)共通のアイデンティティを作りやすいところだと思いますが、それでも、民主主義や福祉政策を常時一緒にやっていけるほどの連帯意識や相互扶助意識を生み出すのは非常に困難です。
逆に言えば、新自由主義者からしてみれば、民主主義や再分配的福祉といった「面倒くさい」ことを要求してくるナショナルな連帯意識など、なるべくなくしたいわけです。国境の垣根を低くし、人の移動を活発化し、域外から移民も連れてきて、異なる人々を混ぜ合わせてしまえば、連帯は生まれにくくなり、自己責任原則が支持を得ます。つまり福祉や民主主義の要求は出てこなくなるでしょう。新自由主義者には大変都合がいいわけです。
長々と書いてきましたが、結局、言いたかったのは、次のことです。
どうも日本では、「EU賛成派 = 自由民主主義的で開明的、前向き」、「EU懐疑派 = 非自由民主主義的で排外主義的、後ろ向き」といったイメージに基づく一面的な論評や報道が多いように感じますが、必ずしもそうとは言えないのではないでしょうか。むしろ、自由民主主義の政治という観点から見た場合、EU懐疑派のほうにも、少なからず、耳を傾けるべき理があるのではないでしょうか。
さて、英国の国民投票の結果はいかに…。
だらだらと失礼しますた…。
<(_ _)>
ーーー発行者よりーーー
【PR】
日本が途上国支援を続けられる訳
消費増税、高齢化、千兆円の政府債務
借金大国の日本が世界貢献できる訳とは・・・
http://www.keieikagakupub.com/sp/38DEBT/index_mag1.php

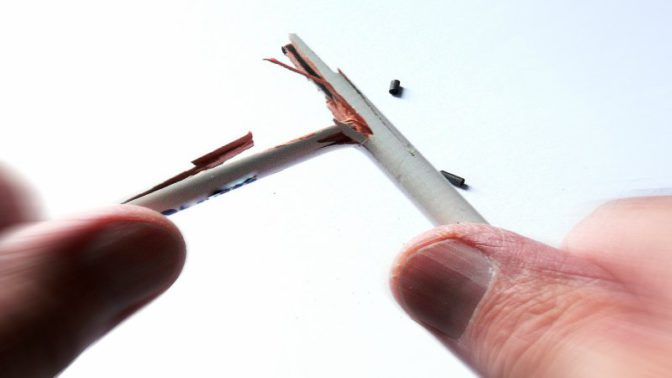
















【施 光恒】「EUが引き起こす分断」への1件のコメント
2016年6月26日 4:30 PM
三橋さんの仰るとおりだと思います。自分達が民主的な選挙で選んだ訳ではない、EUの官僚たちによって作られた規制や法律が、自分達国民の民主的選挙によって作られた政府の法律や規制よりも上に置かれるなどという事になったらたまったものではない。ドイツの主張するような、シリア難民受入れもその一つでしょうが、イギリスのEU離脱が国民投票によってきめられたのも、當然の事だと思います。グローバリズム(=EU とは言えないかも知れませんが)よりナショナリズムの方が、強い、いや強くなければならない、という當然の事が証明された事件だと思いました。TTPの問題とも関わることだと思います。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
コメントを残す
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です