みなさんこんにちは。京都大学の藤井聡です。
今日お話したいのは、下記書籍の「検証」を通して明らかにした、「維新」の問題。
『大都市自治を問う~大阪・橋下市政の検証~』。
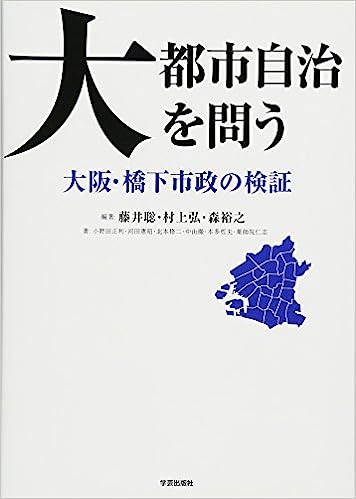
楽天:https://books.rakuten.co.jp/rb/13429363/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_101_0_0
アマゾン:https://www.amazon.co.jp/dp/4761526106
ご案内の通り、今、「維新」(大阪維新の会、および、日本維新の会)は世論の支持を急速に拡大させつつあります。
その背景には、岸田総裁を中心とする与党勢力(自民、公明)に対する不満・不支持が拡大していく中、安全保障政策について信頼性が乏しい「立憲民主党」には、国民における根強い忌避感・嫌悪感があるという事情があります。「自民はもうイヤ、でも立憲はダメ…」というわけで、第三の選択肢としての維新が人気を拡大しつつあるわけです。
維新は、野党の中で安全保障については与党に近い政党ですので、あまり劇的に政治を変えたくない保守的な国民にとって、ちょうど良い「受け皿」になっているわけです。
例えば、先月4日に行われた世論調査では、次の衆議院選挙でどこに投票するかとの質問に対する回答が、『自民党21%、日本維新の会15%、立憲民主党9%』となっています。つまり、今や維新の勢いは自民党に迫る勢いで、現野党第一党の立憲を大きく引き離すところにまできているのです。
しかし、「維新」に日本の政治を任せて良いものなのかどうか、多くの国民が「維新」の実態を知らないままに、「自民はもうイヤ、でも立憲はダメ…だからとりえあう維新にしとこう」という表層的な「とりあえず」な投票行為を行ったとしたらどうなるのでしょうか。
結論から申し上げて、日本がさらなる危機に落ち込むことは確実です。
なぜなら、彼らが過去にやってきた大阪の政治の惨さについて、殆どの国民が知らないからです。
例えば、2015年の大阪都構想が、第一回目の住民投票で否決された直後に、大阪市の行政を様々な角度から研究してきた様々な学者が、2010年に橋下徹氏によって設立された「維新」が、(多くの人々の素朴な認識と裏腹に)大阪で行った改革が如何に大阪の社会、経済、教育、行政を傷つけ、劣化させてきたのかを一冊の本にまとめています。
書籍のタイトルは『大都市自治を問う~大阪・橋下市政の検証~』。
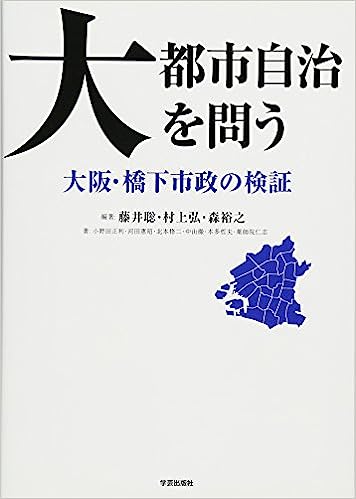
楽天:https://books.rakuten.co.jp/rb/13429363/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_101_0_0
アマゾン:https://www.amazon.co.jp/dp/4761526106
編集者は、地方財政学者の森裕之教授、地方行政・政治学者の村上弘教授と、当方の三名。執筆者は我々3人に加えて、地方行政、地方財政、地方自治、都市計画、防災、教育学、社会学等の地方行政の様々な側面を専門とする学者です。
その内容は以下となっています。
序論 大都市自治の「光」と「影」
第一部 大都市が陥る改革・至上主義
第1章「改革」全体主義の構造 (藤井)
第2章 破壊される自由民主主義 ~政治プロセスの視点から (藤井)
第3章 都市居住と大衆化 (薬師院)
第4章 維新の党 ~右派ポピュリズムの国政への進出 (村上)
第5章 プロパガンダと言論弾圧 (藤井)
第二部 橋下市政は大阪をどう「変えた」か ~政策分野ごとの検証
第6章 教育 【小野田】
第7章 医療・福祉 【中山徹】
第8章 公務員と労組への攻撃 【大阪市政調査会】
第9章 財政 【森】
第10章 防災 【河田】
第11章 都市開発・都市交通 【藤井】
第12章 産業(政策)【本多哲夫】
第13章 「大阪都=大阪市廃止分割」構想の台頭と挫折 【村上】
第三部 大都市自治の未来
第14章 藤井 大都市のプライドに基づく地域間連携・中央政府との協力等
第15章 森 NYの例を引用しつつ、下からの自治を(総合区)等
第16章 村上 「脱東京」の都市政策に向けて ~大阪の魅力と展望等
これらで論じられているのは、次のような様々ない維新政治の「真実」です。
例えば、大阪の教育現場がどれだけ荒廃したのかについては、大阪の教育を長年研究してきた教育学者の小野田正利教授が、「7年余の破壊から立ち上がる人々を支えたい~豊かな大阪の教育の再建を願う教育学者として~」の中で詳しく論じています。
地方財政学を専門とする森裕之教授は、大阪市の財政、ならびに、その「改革」の理不尽さを、大阪市内の自治体の住民自治がどれだけ「維新」行政によって蹂躙されたのかを克明に語りながら、詳細に論じています。
こうした住民自治への橋下市長による激しい攻撃を通して、大阪市における住民共同体が、社会学的な視点から激しく劣化してしまった様子を、社会学者の薬師院仁志教授が多くのデータを活用しながら実証的に描写しています。
一方、大阪市ではコロナによる甚大な健康被害が生じましたが、その背景には、感染症対策のための行政組織を、橋下市政以降、「財政改革」の名の下、徹底的に弱体化し続けたという背景がありました。「維新」行政が如何に理不尽な医療削減を行ったのかを、地方行政が専門の中山徹教授がその実情を「維新政治が進めた医療・福祉の全般的削減」の中で詳述しています。
最後に、大阪は広範なゼロメーター地帯が広がっており、したがって、南海トラフ地震や大型台風で生ずる津波や高潮によって想像を絶する被害が生ずることが分かっています。それにもかかわらず、インフラ投資を忌避し、目先の「改革」ばかりに行政能力を集中させる「維新」政治の中で、今の大阪は次の災害によって取り返しの付かない壊滅的被害を受けることが真剣に危惧されている、という様子を、防災が専門の河田教授が『防災・減災行政上の課題と大阪府政・市政トップの怠慢』の中で子細に論じています。
…この様に、維新が行った「改革」の中身は、その現場の事を知らない一般の大阪市民には殆ど知られてはいなかったものの、それぞれの現場を詳しく見れば、教育も住民自治も地方社会も都市計画も防災も全て激しく「劣化」してしまっていたのです。
それにもかかわらず、かつてタレントでもあった橋下氏が市長の立場で連日記者会見を開き、その「改革」が市民のために良いものであると声高に主張し続け、それを大阪のテレビ局、新聞社が連日連夜報道しまくり、その「改革」行政が、大阪市民にとって素晴らしいモノであるかのようなイメージを喧伝しまくったのです(もちろん、そうしたプロパガンダの実態についても、本書において詳しく分析し、紹介しています)。
こうした「維新」の体質は、今もなお変わってはいません。それが証拠に、今年の統一地方選で彼らが掲げた「身を切る改革」の中身もまた、酷いモノであったことは、下記記事で詳しく紹介されている通りです。
https://38news.jp/economy/24670
ついては、本メルマガ読者の方の中でも、「まぁ、次の選挙は自民にお灸据えるためにも、維新にでもいれとこうか…」とちらっとでも思っている方がおられるなら是非、こうした真実をご認識いただきたいと思います。
そして、「維新」に対して、なんだか胡散臭いなとお感じの方は、その感覚をご吟味いただくためにも是非、維新政治検証の決定版
『大都市自治を問う~大阪・橋下市政の検証~』
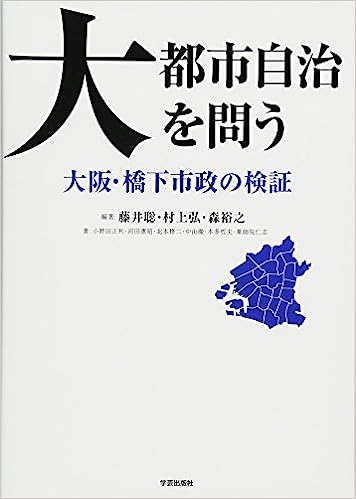
楽天:https://books.rakuten.co.jp/rb/13429363/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_101_0_0
アマゾン:https://www.amazon.co.jp/dp/4761526106
をご一読いただきたいと思います。
是非、よろしくお願いします。
追伸1:『大都市自治を問う~大阪・橋下市政の検証~』は、ここ数年の販売実績が少なく、出版社の方でこの度「絶版」とすることが決定されたと通知がありました。現時点ではまだ出版社に在庫がありますので、ご希望の方は急ぎ、ご手配下さい。もしまとまった部数をご希望の方は、下記のサイトを通して出版社に直接ご要望差し上げて下さい。
https://book.gakugei-pub.co.jp/gakugei-book/9784761526108/
追伸2:本記事は、「表現者クライテリオン編集長日記」からの抜粋・転載です。ご関心の方は是非、ご欄下さい(→https://foomii.com/00178)。


















【藤井聡】「維新」が一体、大阪で何をやったのか? 維新が台頭しつつある今、その〝検証〟の書『大都市自治を問う』を是非、ご一読下さい。への2件のコメント
2023年7月13日 10:22 PM
西部邁さんが昔、
西部邁さん「日本に保守なんていない。日本の保守が保守であるためには敵が必要」
という話をされていました。
本題を話す前に、まずはこちらをご覧ください⇓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1994年10月ニューヨークタイムズ記事
1958年までCIAの極東工作を担当したアルフレッド・C・ウルマー氏の証言が掲載
アルフレッド氏『自民党に対して我々は資金援助をした。CIAは自民党の最初期から同党を支援。内部から情報提供者をリクルートするために資金を使った』
ケネディ政権国務省情報局長ロジャー・ヒルマン氏『1960年代初頭までには、自民党とその政治家への資金援助は確立され、ルーティーン化しており、極めて秘密裡にではあったが米国の対日外交政策の一つとなっていた』
94年11月 産経新聞 当時の自民党総裁アメリカ大使と極秘会談、(アメリカの自民党への)資金援助について大使館に照会があった場合には『インテリジェンスに関するものでありコメントできない』という線で回答してほしい、とアメリカ側のメディア対応に注文を付ける(火消し)
山本太郎議員「日米合同委員会の議事録、公開されてますか?21年度22年度で公開された議事録があるか教えてください」
外務省・宮本慎吾参事官「日米双方の合意がなければ公表できませんが、ご指摘の期間中に公表されたものはございません」
山本太郎議員「はい、ブラックボックスなんですよ」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
それから、こちらも⇓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
文芸春秋4月号寄稿
鈴木宣弘・東京大学大学院農学生命科学研究所教授
筆者は1982年に農水省の国際部に入省し、貿易自由化などの国際交渉に近い部署で仕事をしてきたので、アメリカとのせめぎあいをまじかで見てきた。
農水省に15年ほど勤め、研究者に転じてからも貿易政策に関する研究を行い、自由貿易協定(FTA、日韓、日中韓、日モンゴル、日チリ)の事前交渉にあたる産官学共同研究会には学会の代表として参画している。
また、2011年以降は東大教授としての立場でTPP交渉にも深くかかわっている。貿易自由化や食の安全基準をめぐって数多くの要求を突きつけるアメリカの強引なふるまいは実際に経験してきたことだ。
日本政府関係者は、私が国内農家への「援助」という言葉を口にするだけで震え上がり「その話はやめてくれ」と懇願する。そんな場面は何度かあった。
「アメリカの市場を奪う」と受け止められ、万が一、アメリカ政府の逆燐に触れれば”自分の地位が”危うくなるとの恐れを抱くからだ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
自力で独立を勝ち取ったインドと違って、日本は敗戦占領から「勘弁してもらった国」なので、いまだアメリカの影響力が絶大なようです。なので、日本はアメリカの国益を侵さないように、かつ、財務省の権益を侵さないように立ち回らねばならないので
「国益を考えた政策」
というのは難しい面がある。とはいえ、国民の中には「国益を考えた政策をやってほしい」という欲求はある。つまりは、保守層というやつですね。先ほども言ったように、日本の政治家はアメリカや財務省の顔色を見ながらしか政治ができないので、いわゆる保守層の要求には応えられないわけです。しかし、選挙の時だけは保守層の支持が欲しい。ならばどうするのか?自分たちよりもより左寄りの政治思想を持つ人たちを叩いて
「左翼を叩く我々は保守」
といった感じで保守のフリをすることになるわけだ。なので、日本で保守を自称する連中には敵が必要なわけですね。日曜日の朝の番組に出演していた自民党の政治家が
「保守がなにかもいまだ決められないでいる」
なんて話をしていましたが、要は保守がどういったものかもわかっていないのに保守政治家を自称してきたというわけですね。
そして、そんな保守政治家を支持してきたいわゆる保守層ですが、自分たちが支持してきた政治家が保守ではないとなると、そんな政治家を支持してきた自分たちも保守ではないということになってしまう。自分たちが間違っていたことを認めたくないとなると
保守政治家が保守ではないことを目をつぶってみないようにするしか自分たちのプライドを守るすべがない
そうして、自称保守政治家と共にいわゆる左翼と血で血を洗う闘争によけいに身を焦がしてゆくことになるわけだ。
ただ、最近は自民党の政治家が「保守ではない」という話がバレてきているわけで、見ないふりをしてきた保守層も自民党を応援できない人たちもでてきた。そんな人たちの受け皿が第二自民党などと言われている維新の会だったわけだ。自民党と方針が似ているだけあって移りやすいのもあるのでしょうね。
まあ、政治勢力のマトリクスで右下の政党が出てこない限り
「敵を必要とする保守」
は無くならないし、右下の政党が出てくるためにはアメリカによる内政干渉や財務省の影響力の低下が必要。そのためには軍事も食料もアメリカにおんぶにだっこ状態から抜け出さないといけないのだけれど、現役の官僚さんたちには難しいみたいでしてね…
暗い話をしましたが、森永卓郎さん66歳おめでとうございます!(←最後に明るい話題
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2023年7月14日 11:27 PM
日本国民A「消費税は売り上げ1000万円以下の小規模事業者は払わなくていいのに、売り上げ1001万円の事業者は払わないといけないなんて不公平だ!」
日本国民A「俺は払わされているのにズルい!」
日本国民B「そうだ、だからそんな不公平な税である消費税は廃止しよう!みんなで財務省と戦おう!」
日本国民A「だから、免税を無くして(インボイス制度導入して)あいつらにも俺と同じ苦しみを与えてやってください、財務省様!」
日本国民B「えッ!?」
日本国民A「えッ!?」
自分より立場の弱い者を叩いて憂さ晴らしはするけれど、問題解決に立ち向かう勇気も気力もなく、ただただ「強い方につく」現代の日本国民の姿…いや、今に始まったことではないか。
「アメリカの世話になった方がお得」
「いやいや、これからは中国ですよ。中国の世話になろう!」
こんなことをずっとやってきたのが日本でしたね。自主独立を保とうなどという気はさらさらない連中が政治家・官僚になってるのだから笑えない。伊藤博文が草葉の陰で泣いていますよ。
わたしは、戦前の日本をディスることが多いですが、
「どうにかして日本の独立を保とうとあがいていた」
ことは今の政治と比べれば立派だったと思っています。やりかたはともかくとしてね。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
コメントを残す
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です