From 施 光恒(せ・てるひさ)@九州大学
おっはようございまーす(^_^)/
最近、新しい本を書きました。
『本当に日本人は流されやすいのか』というタイトルです。
角川新書の一冊で、連休明けの5月10日(木)に発売予定です。
https://www.amazon.co.jp/dp/4040820290/
https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g301502001304/
本のオビには、「やみくもな改革を続ける日本は自己啓発にハマった人と同じ」「今こそ『和魂洋才』に立ち戻れ」という文言が書かれています。
この文言からわかるように、この本のテーマの一つは、「失われた20年」を生み出した近年のやみくもな構造改革路線に対する批判です。
日本は、1990年代後半から現在に至るまで、「グローバル・スタンダード」を目指した構造改革路線を続けてきました。
しかし、日本経済はちっともよくなりません。GDPはほぼ横ばいを続け、世界における日本の経済面での存在感は低下する一方です。実質賃金や世帯所得も、1990年代半ばごろをピークに下落を続けています。それに伴って、社会的閉塞感や疲弊感も高まっています。
なぜ、人々の暮らしが良くならないにもかかわらず、日本はやみくもに構造改革路線をとり続けるのでしょうか。さまざまな要因がありますが、一つは、構造改革を行う理由に、純然たる経済的なものだけではなく、実は一種の道徳的命題が含まれているということがあります。日本人の自律性・主体性に関するものです。
普段はあまり意識されませんが、構造改革路線が選択された背景には次のような認識がありました。
「日本人は、自律性・主体性を欠き、同調主義的である。個が確立しておらず、集団主義的であり、政府などの権威に依存する傾向も強い。このような日本人の悪しき人間類型を改造し、欧米人のような自律した個人にしなければならない。社会全体としても、集団主義的なもたれあいの社会ではなく、自律した個人からなる近代的な市民社会へと変革していかなければならない」。
このような一種の道徳的命題が背後にあるため、経済的結果が伴わなくても、構造改革路線が採用し続けられます。
また、市場経済重視の財界人やエコノミストだけではなく、本来なら福祉や社会的平等を重視するはずのリベラル派(左派)的信条の持ち主まで、「市場原理主義」と称されることも多い構造改革路線に結局のところ賛成してしまいます。
この本の目的は、「日本人=自律性・主体性に欠け、同調主義的で権威に弱い」という構造改革路線の背後にある図式を批判し、日本人が自分たち自身をよりよく知り、穏やかな自信を抱けるようにすることです。そして、もっと自分たちにかなった国づくりのあり方とはどのようなものか、それを実現するにはどうすればよいかを考えることです。
本の目次は、次のとおりです。
はじめに
第一章 同調主義的で権威に弱い日本人?
第二章 日本文化における自律性――ベネディクト『菊と刀』批判を手がかりに
第三章 改革がもたらす閉塞感――ダブル・バインドに陥った日本社会
第四章 「日本的なもの」の抑圧――紡ぎだせないナショナル・アイデンティティ
第五章 真っ当な国づくり路線の再生
おわりに
第一章と第二章では、構造改革路線をとり続ける一因である「日本人=自律性・主体性に欠け、同調主義的で権威に弱い」という図式が正しいのかどうか吟味していきます。
この図式が広まるうえで大きな影響力をもったものに、米国の文化人類学者ルース・ベネディクトの著作『菊と刀』があります。ベネディクトの議論の検討を通じて、日本人が本当に同調主義的で権威に弱いのかどうか考察していきます。
本メルマガでも以前、少し部分的に触れたことがあるのですが、結論から言えば、私は、ベネディクトの分析は一方的・一面的だと考えます。日本人は十分、自律性を持つことができるのです。ただ、日本で優勢な自律性の形態やその獲得の過程やメカニズムは、欧米で一般的と考えらえるところのそれらとは少々異なります。ベネディクトは、欧米とは異なる自律性の構想が日本文化に存在することをきちんと認識できず、日本人が自律性をもたない、また目指してもいないと誤解してしまったのです。
このように論じながら、いわば日本型の自律性の理念と呼びうるものはどのようなものであり、どのようなメカニズムでそれが身に付けられるのかを説明していきます。
第三章と第四章では、欧米型の自律性の理念を無批判に受け入れ、構造改革路線を選択してきた結果、日本社会が陥った苦境について検討しています。特に、改革すればするほど閉塞感や無力感が社会に蔓延していくという現在の倒錯した状況がなぜ生まれるのか、その理由を解き明かすことに挑んでいます。
第三章では、「ダブル・バインド」「価値観の自己矛盾」という概念や「ひきこもり」をめぐる言説などを手掛かりに、日本の苦境について読み解きます。
第四章は、やはり日本の苦境について、1990年代に流行ったホラー小説(映画)の『リング』などに触れつつ、民俗学的・文化論的な視座をまじえて論じます。
最後の第五章では、第三章と第四章で明らかにする問題を解消するにはどうすればいいか、その方策を考えます。キーワードの一つは、前述のオビにあるように「和魂洋才」です。人々がよりいきいきと暮らせる安定した社会を取り戻すためには何が必要かを検討していきます。
今回はまるまる新刊の紹介・宣伝になってしまいました…
f(^_^;)
ぜひ読んでくだされば幸いです。
<(_ _)>












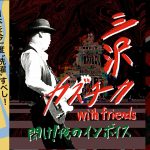





【施光恒】本当に日本人は流されやすいのかへの2件のコメント
2018年4月27日 11:50 AM
日本人の特性だけで、この失われた20年を語るから理解できないんでしょう。
明白に外資による日本叩きと日本食いによる、配当増の為の、雇用の流動化(笑)、つまり非正規雇用という名の半失業者の量産。
小泉改革も、民主党事業仕分けも、アベノミクスも、全部、ゴールドマン等の欧米投資家が影に日なたに口を出してますよね。
こうした勢力に日本に先だって食い荒らされたのが、欧米や韓国。
安倍の馬鹿は年金までファンド化して、欧米投資家さまの為に中国から大量の移民も結果的に受け入れて。
今まで、安倍政権を、ネオコン&ネオリベの保守(笑)と思ってましたが、隠れ親中政権も兼ねていたんですね。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2018年4月28日 4:03 PM
よく日本は「トップが無能で、社員が優秀」などと言います。
真偽はともかく、「大多数の人が、上の意見に左右されず主体的に仕事をしている」と評されているとも取れます。
現に、開発現場では多くのエンジニアたちが主体的に働き、議論では海外のエンジニアをやり込んでいる場面に多く遭遇してきました。
むしろ米国では、契約によって職務範囲が日本より厳しく定められており、また上司に生殺与奪の権限があるため、エンジニアは委縮しがちです。
私は開発の現場で仕事をしてきた限り、日本人が「自律性・主体性を欠き、同調主義的」と感じたことはありません。
ちなみに私は、「自律性・主体性、そして個の確立が大事だ!」と唱える人たちが、米国の言う通りに構造改革を推進しているという矛盾になぜ気付かないのか?不思議でなりません。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
コメントを残す
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です