From 青木泰樹@京都大学レジリエンス実践ユニット・特任教授
現在、政府は「経済再生なくして財政健全化なし」を基本として、2020年度における
名目GDP600兆円の達成と基礎的収支(PB)の均衡を目指しています。
「経済の健全化」の達成が重要であって、財政健全化など付随的な問題にすぎません。
特に緊縮財政によってGDPを低下させるPB目標など百害あって一利なし。
にもかかわらず、相変わらず政府方針に盛り込んでいるところに、現政権の中途半端さが垣間見られます。
ただし本日は財政論議に立ち入らず、名目GDPの600兆円達成へ向けたシナリオについて考えたいと思います。
「名目GDP600兆円」の論拠となっているのは、内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」です
(平成29年1月25日経済財政諮問会議・資料2-2参照)。
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/index.html#tab0215
この試算は、経済・財政・社会保障を一体的にモデル化した「内閣府の計量モデル(「経済財政モデル」)」に基づくものです。
内閣府は、今後の経済状況に関し、楽観的なシナリオと現状維持のシナリオを想定し、それぞれのケースの試算をしています。
経済財政政策が着実に効果を発揮する「経済再生ケース」と、現状維持が継続する「ベースラインケース」です。
今回取り上げるのは、名目GDP600兆円を実現する経済再生ケースです。
それは、日本経済が「デフレ以前の力」を取り戻した場合を想定したものです。
具体的には、中長期的に経済成長率が実質で2%、名目で3%以上となり、インフレ率が2%程度で安定的に推移するケースです。
ただインフレ率2%で実質成長率が2%なら、名目成長率が4%ないと理屈に合いませんが、それは不問に付しておきましょう。
さて、この経済再生ケースには三つの前提が置かれています。
第一に、全要素生産性(TFP)の上昇率が足元の「0.8%」で2016年度まで推移した後、2020年へ向けて「2.2%」へ上昇すること。
第二に、女性・高齢者を含め労働参加率が徐々に高まっていくこと。
第三に、世界経済成長率がIMFの世界経済見通しに基づいて推移すること、です。
言うまでもなく、この前提のうち重要なのは、技術進歩率を示すTFP上昇率です。
TFP上昇率が「2.2%」になることが、GDP600兆円達成のために必要なのです。
その数値は、1983年から1993年の平均ですから、まさにバブル期におけるTFP上昇率を前提にしているということです。
そのような急激な技術進歩が、果たして新年度以降に生じるのでしょうか。
主流派経済学者、エコノミスト、経済マスコミは、異口同音に「そんなことが起こるはずがない」と内閣府の再生シナリオに懐疑的です。
彼らは、生産性の向上は一朝一夕にできるものではなく、地道な規制緩和を中心とする構造改革によって長期的に達成されるものだと考えているからです。
彼らの依拠する供給側の経済学からすれば、当然でしょうね。
しかし、実現できるのです。
そのことを内閣府に助言するために、本日のコラムを書いています。
前回、GDP統計の改訂によって、これまで経費に計上されていた「研究開発(R&D)への支出」が総固定資本形成(投資)に変更された結果、
内閣府の算出する潜在成長率が「0.4%」から「0.8%」へ上昇したことを指摘しました(他の要因も含めて)。
それによって、「総需要の継続的増加は、潜在成長率を上昇させる」という私見(潜在成長率に関する青木説)が実証されたとお話ししました。
https://38news.jp/economy/08212
ただし、内閣府が自前の潜在成長率の定義に固執する限り、私の説を受け容れないでしょう。
その原因が、内閣府固有の誤った経済観にあることを説明します。
経済学者が各自の依拠する「経済学説」というメガネ越しに現実経済を見ているのと同じように、
内閣府もまた「定義」というメガネ越しにGDPおよび経済成長を見ています。
(参照 http://amzn.asia/gvdXakV)。
ただ内閣府メガネには、「現実GDPを見るメガネ」と「潜在GDPを見るメガネ」の二種類あることが混乱を生じさせる原因です。
内閣府は、名目にせよ実質にせよ、現実GDPを「国民経済計算(GDP統計)」によって算出しています。
すなわち現実GDPを、三面等価の原則に従い、経済の需要面の総和(総需要)として算出しています。
他方、潜在GDPは供給側の「成長会計に基づく生産関数モデル」によって算出しています。
過去平均の労働投入量、資本投入量およびTFPによって潜在GDPを算出し、
そうした諸資源の投入量の増加および技術進歩率によって潜在成長率が決まると考えています。
この真逆の算出方法が内閣府の潜在成長率解釈の誤りを生む本源なのです。
現実GDPは総需要が決めるのですから、経済成長率は総需要が伸びれば上昇します。
他方、潜在GDPの決定要因の中に需要項目は入っていませんから、潜在成長率は総需要が伸びても上昇しません。
内閣府は、総需要の動向と潜在成長率は無関係と考えているわけです。
今般、GDPの推計方法を国際基準「2008SNA」に準拠したことにより、総需要は30兆円増加し、現実GDPも同額上方改訂されました。
その結果、潜在成長率は「0.4%」から「0,8%」へ上昇しました。
変だと思いませんか。
総需要と無関係のはずの潜在成長率が、なぜ上昇したのでしょう。
内閣府は、「直近のGDP成長率が上方改訂されたため、足下のGDPのトレンドが上向き、全要素生産性の伸びとして潜在成長率の推計に反映された結果であり、総需要を増やせば潜在成長率は伸びるとの指摘は当たらない」と述べています(平成29年2月24日「内閣衆質193第73号」・14についての答弁書)。
内閣府は、「総需要の増加=全要素生産性(TFP)の上昇」と解釈することで、総需要の影響を排除しているのです。
総需要の動向は、潜在成長率と無関係だと言い張っているのです。
潜在成長率の決定因に総需要が入っていないための苦肉の言い訳ですね。
内閣府がそのように強弁するのであれば、私の助言はただ一つ。
「名目GDP600兆円の達成へ向けて、TFPを2.2%に上昇させるためには、公共投資を中心とする総需要拡大策を継続的に図ることだ」、と。
ついでに内閣府のGDPの定義に関するダブルスタンダードを解消する方法も付け加えておきましょう。
それは、現実GDPと潜在GDPの関係を一歩踏み込んで考えることです。
内閣府は両者を無関係と考えているために、何時になっても実相が見えてこない。
先述したように、内閣府の定義では、潜在GDPを決定する要因は過去平均の労働および資本の投入量とTFPです。
ここで、「過去平均の諸資源の投入量は何によって決定されたか」を考えることが肝要なのです。
決定要因を考えなければなりません。
それを考えないため、「潜在GDPと総需要は無関係」という結論が出てくるのです。
経営者であればだれでも、需要予測をして、生産計画を立て、そして諸資源の投入量を決めているのです。
先ず需要(予測)ありき、なのです。
そう考えれば、過去平均の諸資源の投入量が総需要によって決定されていることは明らかでしょう。
現実GDPの過去平均が潜在GDPなのです。
同様に、潜在成長率は「経済成長率の天井」でもありません。
それが天井となるのは、諸資源の投入量が総需要に影響されない状況、すなわち既存の諸資源のストックが全て投入され、かつ生産物が全て売りつくされる状況だけです。
すなわちセイ法則が成り立つ世界です。
しかし、現実世界は不確実性を除去できないため、セイ法則は成り立たないのです。
今後、総需要が増加していけば、確実に経済成長率は上昇します。
それを現在の内閣府流の解釈に従えば、「TFPが上昇し潜在成長率は上昇する」ということになるのでしょう。
しかし、そうした誤魔化しは止めるべきです。
今般のGDP統計の改訂によって、総需要が増加しGDP成長率が上昇した結果、潜在成長率が上昇した事実を、内閣府は虚心坦懐に受け容れるべきでしょう。
「財政を拡大すれば、現在の潜在成長率が低くとも経済は発展することができる」ことを認識すべきなのです。












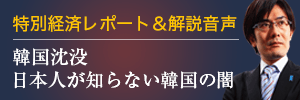
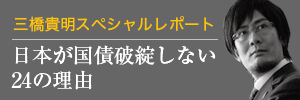



コメントを残す
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です