From 柴山桂太@滋賀大学准教授
————————————————————–
●これは経済学者のルサンチマンの結果なのか?「EUの闇」とは?
https://www.youtube.com/watch?v=DID9wg3PIVo
————————————————————–
今年は、いろいろ記念すべき年にあたるようです。第一次大戦の開戦から100年目にあたるという話はよく知られていますが、もう一つ、ブレトンウッズ会議が開かれてから70年目の年でもあります。
ブレトンウッズ会議が開かれたのは、第二次大戦中の1944年7月。44カ国の代表がアメリカ・ニューハンプシャー州のブレトンウッズに集まって、戦後の通貨・金融体制について話し合いました。主役はアメリカとイギリスで、アメリカ代表のホワイトと、イギリス代表のケインズが国際通貨体制のあり方をめぐって、激しいバトルを繰り広げた話は有名です。(交戦中だったドイツと日本は、当然ながらこの会議に参加していません。)
バトルといっても、実質的な主導者はアメリカでした。第二次大戦でイギリスはアメリカに膨大な借金を負っており、アメリカの援助なしには戦争の継続もままならない状態にあったからです。イギリス代表団は、アメリカに援助をお願いしつつ、来る通貨体制においてイギリスの指導的地位を守る(=アメリカ・ドルの支配を挫く)という絶望的な闘いを強いられました。第二次大戦は、米英の金融覇権を巡る水面下の闘いでもあったのです。
この交渉にあたってケインズが編み出したのが、「清算同盟案」です。これは、人工通貨バンコールを創設して、国際決済を超中央銀行が一元的に管理するという提案ですが、圧倒的な金保有を背景に、いまや世界の経済秩序を差配できる立場となったアメリカが、そんな提案においそれと乗るはずもありません。ブレトンウッズ会議は、外交的に見ればアメリカの圧勝でした。今日につながるドル支配の構図は、この会議によって決定的なものとなったわけです。
それから70年がたち、ブレトンウッズ会議に再び注目が集まっているのには、いくつかの理由があります。まず、昨今の世界経済の混乱で、戦後のブレトンウッズ体制の再評価が始まっているということ。ブレトンウッズ体制は、その期間(〜70年代前半)がちょうど各国の高度成長期と重なったこともあり、いまも一定の支持を集めています。資本移動の国際管理の下で、巨大な金融危機の発生も抑え込まれていました。
以前、紹介したD・ロドリックは、世界経済の混乱の原因となっているハイパー・グローバリゼーションを抑制する一つのモデルとして、ブレトンウッズの理念を好意的に取り上げていました。
http://www.amazon.co.jp/dp/4560082766/
http://honto.jp/netstore/pd-book_25973716.html
また今年の7月には、BRICSが独自の開発銀行や、共同基金の設立を決めました。これにはIMFや世界銀行という「ブレトンウッズ機関」への挑戦という意味合いがあるとされ、アメリカ主導の金融秩序への対抗が目指されています。
もっとも、BRICSは一枚岩ではないため、前途は多難です。
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0FL0YJ20140716
また共同基金は出資額も少なく、またドルでの出資なので、現状ではIMFを脅かすような存在には到底なり得ないでしょう。
http://www.project-syndicate.org/commentary/barry-eichengreen-is-bullish-on-the-group-s-new-development-bank–but-not-on-its-contingent-reserve-arrangement
いずれにせよ、巨大な金融危機が発生し、また新興国がアメリカ(など先進国)の金融政策に振り回されやすくなっている中で、いまの世界経済体制が本当にこのままでいいのか、疑念が高まっているのは事実でしょう。歴史の見直しが言われているゆえんです。
そんな中、面白い本が出ました。
ベン・スティル『ブレトンウッズの戦い ケインズ、ホワイトと新世界秩序の創造』(日本経済新聞社)
http://www.amazon.co.jp/dp/4532356024
http://honto.jp/netstore/pd-book_26346579.html
この本は、ブレトンウッズ会議の内幕を、ホワイトとケインズという二人の人物に焦点を当ててて描いたドキュメントで、この問題に関心がある向きには実に興味深い読み物です。(ただし分厚い上に、細かい事実が並んでいるので、読み通すには根気が必要かもしれません。)
日本では、ケインズの名声もあり、ブレトンウッズというとケインズを悲劇の主人公として美化する傾向がありますが、本書は違います。むしろ絶望的な闘いを強いられたケインズが、次第に判断を狂わせていく様が描かれています。
ケインズが経済学者としての世界的名声によって周囲から持ち上げられつつも、ホワイトの策略にはめられて、後で取り乱したりする姿は、事実に基づいているだけにとてもリアルです。ブレトンウッズ会議と、それに前後する英米金融交渉の激務がたたって、ケインズは寿命を縮めてしまいました。(1946年に63歳で亡くなりました。)
もう一人の主人公、ホワイトについても詳しく書かれています。この人物、歴史に名を残している割には謎が多いことで知られており、特にソ連のスパイだったという疑惑が有力視されてきました。本書でも、この事実が独自の調査によって掘り下げられています。ホワイトがソ連への情報提供者だったことは間違いなく、いくつかの重要な局面でソ連への利益誘導をはかった疑惑についてもほぼ黒に近いグレーとされています。
ただしそれらが、ソ連側からの命令によって行われていたのかどうかは、確実な証拠がないために分かりません。本書の記述に従うと、ホワイトは自らの思想信条に基づいて、自発的にソ連への協力を行っていたというのが真相に近いようです。イギリスを帝国の座から追い落とし、アメリカの覇権を確立した上で、米ソによる新しい世界秩序を構築する。そういう青写真を持っていたように見えます。
ところがホワイトの夢も実現しませんでした。トルーマン政権になって冷や飯を食わされたこと、米ソ対立が決定的なものになったこと、などが理由です。その上、「赤狩り」にあって、ホワイトも査問に掛けられ、1948年に55歳で命を落とします。(自殺説もあります。)つまりケインズもホワイトも、自らの理想を達成することなく、時代の圧倒的な力に押し流されながら、この会議の後で非業の死を遂げたわけです。
本書の著者は、ブレトンウッズ体制が戦後世界に果たした役割を必ずしも美化しません。IMF協定は現実にはほとんど機能せず、資本移動の管理はすぐに有名無実化しました。戦後の経済復興にはブレトンウッズ協定ではなくマーシャル・プランの貢献が大きかったというのが著者の評価です。
ただそれでも、ブレトンウッズ会議が、二〇世紀の興味深いドラマであったことには違いありません。固定相場か変動相場か、ドル基軸か世界通貨か、多国間主義が二国間主義か、自由貿易か保護貿易主義かといった現代につながる論点は、すべてこの時期に議論されていたからです。
国際通貨体制は、今のドル支配の構図が簡単に終わるとは思いませんが、かといって永遠に続くという見込みもありません。そもそも国際通貨体制は(国際金本位制の誕生から数えると)150年ほどの歴史しかなく、その時々の国際情勢によって大きく左右されます。世界経済の今後を考えるとき、ブレトンウッズ体制という「実験」は、その失敗も含めて、何度も立ち返ってみるべき歴史の教訓と言えるでしょう。
PS
ユーロの闇とは? 三橋貴明が無料ビデオで解説
https://www.youtube.com/watch?v=DID9wg3PIVo












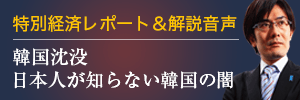
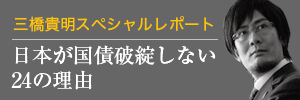



コメントを残す
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です