From 柴山桂太@京都大学准教授
———————————————
【無料video】
失業者続出!?中国経済の実態とは?
https://www.youtube.com/watch?v=s098BvnKKgU
マイナス金利でデフレ脱却は可能か?
https://www.youtube.com/watch?v=_0n2q8asFVQ
———————————————
最近、読んで面白かった本を紹介します。
松林薫『新聞の正しい読み方』NTT出版、2016年
http://www.amazon.co.jp/dp/4757103638
http://honto.jp/netstore/pd-book_27672965.html
著者は日経新聞の元記者で、記者時代の経験から、新聞情報の読み方を指南しています。記者がどんなやり方で取材し、ニュースがどうつくられているのか。新聞に固有の表記ルール、例えば「政府高官」の発言とは誰の発言なのか、といった具体的なエピソードが盛りだくさんで読ませます。
印象に残ったのは、新聞は実は影響力を失っていないという指摘。若者を中心に新聞無講読層が増え、新聞社の経営が苦しくなっているのは確かですが、ではわれわれが新聞の情報に触れていないかというとそんなことはない。ネットのニュースは新聞社が提供しているものがほとんどですし、テレビの朝昼の情報番組も、朝刊や夕刊の記事をそのまま読み上げたり、新聞社の解説委員が解説したりしています。
つまり紙の新聞は購読されなくなっているのに、新聞の持つ情報発信力は減るどころか、むしろ増えているとも言えるわけで、だから新聞を取っていない若者も、新聞についてもっと興味を持った方がいい、というのが本書の問題意識です。
新聞の影響力は減るどころか増えている、という指摘は重要だと思います。テレビやネットがこれほど普及した現在では、紙の新聞など風前の灯火で、いずれ終わるメディアというのが一般的な見解だと思います。その割には、新聞の持つ影響力はいまも衰え知らずで、特に世論形成という面では、新聞の持つ力は他を圧しています。
その理由は、ニュースの生産というもっとも重要な機能を、今も新聞が担っているからです。
本書にもあるように、記事ができるまでに取材から裏取りから校正から何から、新聞社は膨大なコスト(人手とお金)をかけています。ニュースの解説はテレビやネットもできますが、ニュースの生産となると限界があります。以前、別の本でニュースの八五%は新聞社が発信しているというアメリカの研究を読んだことがありますが、日本も似たようなものでしょう(CNNのようなニュース専門チャンネルがない分、もっと多いかもしれません)。ニュースの生産は、いぜん新聞が独占しているのです。
もちろん、新聞社の経営が悪化すれば、ニュース生産にかかるコストも削減せざるをえません。新聞社のビジネスモデルが限界に来ているのは間違いないところでしょう。しかし、それに変わる新しい仕組みはまだ生まれていない。すでに役割を終えたように見える紙の新聞が、いまなお社会に隠然たる影響力を発揮しているのはそのためです。
新聞が権力だということになれば、当然、その権力を利用しようとする力も働きます。政治家や役人、大企業は都合のいい情報を書いてもらおうとしますし、市民団体は新聞の力を使って自分たちの主張を拡大しようとするでしょう。新聞は、そうした力がせめぎ合う場です。一つ一つの記事について「誰が」「どのような意図」をもって情報を発信しているのか、読者が見分ける力をもたなければなりません。
現代社会は、世論が決定的な力を持ちます。行政も司法も、世論には逆らえませんし、企業も世論を敵に回してまで商売はできません。世論を左右できる新聞は、非常に大きな権力を持っていると言っていいでしょう。それほどの力を持っているにもかかわらず、新聞の社会における位置づけはあいまいで、政府のように公法に縛られていませんし、企業のように市場競争によって律せられているわけでもありません。だからこそ、読者が新聞を批判的に読む必要があるわけです。
今後、新聞業界の再編が進み、新聞社の数も新聞記者の数も減ることでしょう。軽減税率を適用したところで、この流れが変わるとは思えません。だからといって新聞のもつ権力がなくなるとは限らない。ここに、新聞という社会装置の不思議さがあります。ニュースの生産を新聞社が担うという構図が変わらない限り、媒体が紙から電子に変わっても、世論形成への新聞の影響力がなくなることはないでしょう。報道の適切さを評価する姿勢を、読者が身につけなければならないゆえんです。
新聞リテラシー(批判的な読解)について書かれた本はたくさんありますが、新聞リテラシーをなぜ持たなければならないのか、その理由にまで踏み込んだ深い分析が行われているという点で、本書は類書にない説得力を備えています。新聞に興味があるという読者だけでなく、新聞なんか大嫌いという読者にもオススメできる良書です。
ーーー発行者よりーーー
【PR】
2016年2月、日本銀行は史上初の「マイナス金利」を導入した。
今回、日銀が導入したマイナス金利とは、市中銀行が持っている日銀当座預金の一部の金利をマイナスにするというものだ。これまで年利0.1%の金利がついていた日銀当座預金だったが、逆に年0.1%の金利を支払う(手数料を取られる)ことになる。
当然、銀行の収益を圧迫する要因となるのだが、その狙いはどこにあるのか。また、狙いどおりに事が運ぶのか。
三橋貴明は「家計と銀行の負担が増え、国債の金利が今以上に下がるだけ」と断じる。また、「円高はいっそう進むだろう」と予測する。
その根拠は? 今後への影響は?
そもそも「マイナス金利」政策を正当化する理論自体に問題があり、その奥にはお決まりのいわゆる「国の借金問題」があるという。
マイナス金利の解説からその影響、導入の背景、さらには経済成長の問題、そしてアメリカ大統領選挙にまでつながっていく一連のストーリーを、三橋貴明が詳述する。
『月刊三橋』最新号
「マイナス金利の嘘〜マスコミが報じない緊縮財政という本当の大問題」
http://www.keieikagakupub.com/sp/CPK_38NEWS_C_D_1980/index_mag.php

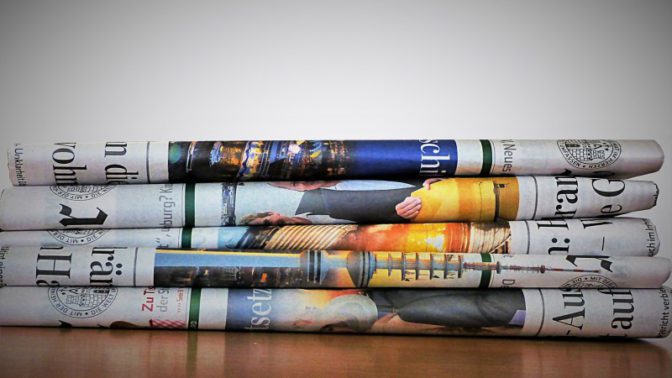
















【柴山桂太】新聞の正しい読み方への3件のコメント
2016年3月31日 4:35 PM
>それほどの力を持っているにもかかわらず、新聞の社会における位置づけはあいまいで、政府のように公法に縛られていませんし、企業のように市場競争によって律せられているわけでもありません。だからこそ、読者が新聞を批判的に読む必要があるわけです。柴山先生全く同感です。朝日新聞を批判するとよく左派的な人達が朝日新聞を批判してる人達を批判してますが。新聞って何だかんだ言って第四の権力と言われてます、しかし企業や政府のように何かしら問題のある事やっても新聞は何かしらペナルティーがある訳じゃありません。新聞は情報が商品な訳ですから誤った情報(商品)が売り出されればリコールするのが当然だと思います。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2016年4月1日 3:56 PM
インターネットの掲示板で議論する際に、ソースを出せと言いますが、そのソースは大抵新聞の引用なんですよね。新聞社は、本業ではない業種の方が儲かっていたりするようですね。しかも、新聞をつかって、宣伝できるし。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2016年4月2日 1:54 PM
イエロージャーナリズム♪発行部数を伸ばすためにイエロージャーナリズムと呼ばれる事実よりもセンセーショナルさを優先し、時には事件を偽造したりする誇大報道を続け、会社を大きくしていきました。とさ。。。南京で何百万も虐殺したり とか朝鮮から売春婦を何十万も無理やり連れてきたり とかあげくの果てには 珊瑚に落書きして の 自作自演 捏造 報道。。。これぞまさに 押しも押されもせぬイエロージャーナリズム の 王道♪目新しい newsなど そうそう有るものではないでしょうしいわゆる newsなど ないのが 健全な世の中「昨日も本日も さしあたって newsは ございません 恙無く 一日を過ごせたことに 感謝します」と印刷された新聞紙 が ナプキンとしてコンビニにでも 置かれる日の一日も早く 訪れるようになることを心の 底から 願っているのだ♪
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
コメントを残す
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です