From 青木泰樹@京都大学レジリエンス実践ユニット・特任教授
財政健全化に向けてとるべきは、「先憂後楽」。
財政制度等審議会(吉川洋会長)は、半年ごとに財務大臣に建議をしていますが、直近の建議の中で、財政健全化の基本的考え方としてこの故事を使っています。
元来の意味から若干離れますが、「先に苦労・苦難を体験すれば、後で楽になれる」と言いたいのでしょう。
もちろん、その含意は「少しでも早く増税および歳出削減を断行し、財政健全化を図れば将来不安は払しょくされる」ということです。
恒例行事のように、毎回毎回、2020年度までの基礎的収支(PB)バランスの達成、すなわちプライマリー赤字の解消を唱え続けています。
さらに今回はハードルを上げて、PBに利払い費も加えた財政収支のバランスを目標にすべしとの提言も加えております。
まさに財務省の意を忖度(そんたく)した建議と言えましょう。
財制審を主導するのは著名な経済学者たちですが、彼らはなぜこれほどまでに財政均衡にこだわるのでしょうか。
今回は、財政均衡の経済学的論拠について考えます。
結論から言えば、彼らは主流派経済学の論理に縛られ、現実が見えなくなっているということです。
もしくは意図的に見ようとしないのかもしれません。
経済学者は「経済学の見地からすれば・・」という前置きをよく使いますが、この常套句を聞いたときは「現実には当てはまらないが・・」と彼らが言っていると解釈するのが適切です。
今回、彼らの言うことを真に受けてはならない理由を具体的にお話ししましょう。
一般論として「現実経済が景気変動を免れないとすれば、財政運営は中長期的視点からなされるべきだ」と考えることは、誰にも受け容れられる極めて自然な見解に思えます。
ここから話を始めましょう。
ただし主たる財政観は二つありますので、各々の考え方の違いを先に示しておきます。
第一に、景気変動によって税収が変動する一方、政策経費は固定されているものが多いため、「出」と「入」のギャップを中長期的にならすべきだという財政観。
これは個人の家計運営にも同通するため、一般に普及している財政観です。
それをここでは、「伝統的財政観」としておきます。
第二に、景気変動によって国民経済は健全な状態から乖離(かいり)するため、そのギャップを埋めるように財政運営をすべきだという現代貨幣理論(MMT)に基づく財政観。
例えばデフレ不況、インフレの高進、金利の高騰といった好ましくない経済状況から脱却すること、すなわち「経済の健全化」を財政運営の目的とし、その達成手段として税と政策経費を用いるという考え方です。
具体的には、景気状況に応じた増減税、財政出動の実施および金融市場への介入等です。
この場合、「出」と「入」のギャップをならすこと、すなわち財政の健全化はもはや目的とはなりません。
それを「機能的財政観」としておきましょう。
財制審の経済学者は、伝統的財政観を主流派経済学の論理に当てはめることによって、短期的な財政均衡を目指すPB目標を掲げています。
彼らの論理を、順を追って説明しましょう。
新古典派経済学の後継の諸学説、マネタリズム、新しい古典派、ニュー・ケインジアン等を主流派経済学と呼びますが、その特徴を一言で言えば、「個人(ミクロ)の主観的満足を求める合理的行動が全体(マクロ現象)を決める」ことです。
逆から見れば、マクロ状況とは全ての個人(合理的経済人)が満足した状態である、と考えているのです。
「この経済学の見地からすると・・、現実経済は常に理想状態にある」ことになります。
学説によって「景気変動は生じない」、「景気変動下においても個人は満足している」、「景気変動に対して何もしなくとも、すぐに理想状態に復帰する」と三通りありますが、本質は変わりません。
すなわち主流派学者は、景気変動が存在しない、もしくは存在しても考慮する必要のない状況を前提に財政均衡を考えているのです。
現実には「景気変動→税収の変動→PB(もしくは財政)赤字や黒字の発生」という因果の連鎖があるのですが、主流派学者は「理想状態=PB(財政)均衡」としか考えません。
景気状況が原因で、結果的にプライマリー不均衡が生じたことを考慮しないのです。
財制審の学者たちは、現実のPB赤字の発生に直面して機械的に増税と歳出削減を唱えていますが、そうした施策がマクロ経済にどれほどの悪影響を及ぼすかについて論じません。
彼らの想定するマクロ経済が、常に完全雇用の達成された理想状態だからです。
つまり、「経済学の見地からすると・・、悪影響は出ない」と考えているのです。
現在の日本経済は未だデフレから脱却しておりませんが、その原因が2014年の消費税増税にあることは衆目の一致するところです。
当時、彼らは全員、PB赤字解消のための消費税増税に大賛成でしたが、それもこの主流派経済観に基づくものです。
財制審の学者の建議どおりに増税した結果、「先憂後苦」になってしまいました。
先に苦難を経験して、後でも苦しんでいるのが日本経済の現状なのです。
さらに主流派学者が、経済の健全化を最優先に考える機能的財政観を軽視する理由も同じです。
彼らが経済の健全化の達成された状態から議論を始めているためです。
機能的財政観の「目的」は、彼らの「前提」なのです。
経済の健全化など考慮の埒外(らちがい)なのです。
それでは、彼らはなぜ財政均衡を唱えているのでしょう。
それは理想状態を示す理論モデルと整合性を保つためです。
単に学問的理由から発しているのです。
以前から論じているように、財政均衡主義が機動的な財政運営より優れていることは論証されていませんし、今後もできません。
なぜなら、それは新古典派の経済モデルの前提である「政府の予算制約式」にすぎないからです。
モデル構築に際して初めから決まっているのですから、証明のしようがないのです。
その辺りの事情を見ておきましょう。
主流派モデルの目的は、予算制約下で、個人が最も満足した状態に達する条件(もしくは最適経路)を示すことです。
予算制約がない、すなわち無限に予算があるならば経済問題は生じません。
好きなだけ買えるわけですから経済学の入り込む余地はないのです。
個人の一生の予算制約を決めるのに用いられるのが、生涯所得(Yp)です。
ただし個人が自由に使える所得は、生涯所得から生涯に支払う税金総額(Tp)を控除した可処分所得です。
それが、個人の予算制約である「恒常所得(Yp-Tp)」です。
ここで「恒常」という用語は、ミルトン・フリードマンの「恒常所得仮説」に由来するもので、予想される全期間の合計額(正確にはその現在割引価値)を示す概念です。
例えば、恒常消費(Cp)は生涯を通じての消費総額、政府支出の恒常水準(Gp)は将来にわたる政府支出の総額といった具合です。
合理的な個人は恒常所得を使い切って生涯を終えます(もしも、使い残しがあれば悔いが残るため)。
所得を使い切ることを横断性条件と言い、それが個人の合理性を担保する条件です。
ここでは「Yp-Tp=Cp」で示されます。
これが個人の予算制約式です。
他方、生涯所得(Yp)はどのように得られるのでしょう。
所得とは生産(量)の分配面を示す概念で、生産(量)は市場の需給均衡(一致)で決定されます。
ここでの市場均衡式は、「Yp=Cp+Gp」となります。
個人の予算制約式と市場均衡式から、「Tp=Gp」が得られます。
これが政府の予算制約式で、「税収総額と政府支出総額は一致しなければならない」ことを意味します。
これが財政均衡なのです。
この政府の予算制約式は、個人の予算制約式から導かれたものですから、最大満足を目指す個人の合理的行動と整合的なものです。
全ての個人が満足した状態が理想状態ですから、そのために財政均衡が必要になるというのが主流派モデルの想定です。
こうした予算制約に従う、すなわち個人の合理的行動の妨げにならないように、財政均衡を図る政府を「リカード型政府」と呼びます。
リカードは、「政府が政府支出を増加(ΔG)させても、個人は将来の増税(ΔT)を予想するので消費を増やさない」という中立命題で有名な経済学者です。
恒常所得仮説に従えば、恒常所得(Yp-Tp)に変化がなければ消費は変わらないということです。
最近話題の「物価水準の財政理論(FTPL)」は、政府がこの予算制約に従わない場合(非リカード型政府と言います)にどうなるかという話なのですが、詳細は別の機会に譲りましょう。
さて、この主流派モデルに立脚すれば、財政政策は無効となります。
一時的な減税や財政出動をしても将来を見通せる(完全予見と言います)合理的経済人には通用しません。
それでは、政府支出の恒常水準(Gp)を引き上げた場合はどうでしょう。
継続的な財政出動の場合です。
しかし、それも無駄です。財政均衡に阻まれるからです。
確かに市場均衡式から、Gpの増加分だけYpは増加します。
しかし、政府の予算制約式より「Gpの増加=Tpの増加」とならねばなりません。
すると可処分所得(Yp-Tp)はTpの増加分だけ減少しますから、元の木阿弥になるのです。
主流派学者が財政出動に対して冷淡なのは、ひとえに彼らの理論モデルに基づくものです。
主流派経済学、財政均衡、財政政策の否定は、セットなのです。
しかし、その論理は極めて厳しい仮定に基づくものですから現実に適用することは不適切です。
現実経済が理想状態だとしたら、不平不満を言う人は一人もいないはずです。
不確実性がある以上、個人は将来を見通すことはできません。
それゆえ自分の恒常所得をわかる人は誰もいません。
最後に、この主流派モデルの奇妙な構造を指摘しておきましょう。
それは個人の寿命と政府の存続期間が一致していることです(「個人の寿命」を「一族の寿命」に置き換えただけの世代重複モデルも本質は同じ)。
究極の個人と政府の同一視。
個人の家計と政府の財政を同一視することから、財政問題に関するさまざまな誤解が生じているのですが、その本源は主流派モデルにあるということです。
「現実経済」を「経済学の世界」と混同する経済学者ほど、罪深い存在はありません。













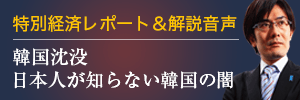
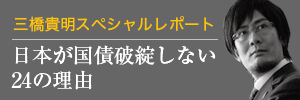



【青木泰樹】財政均衡主義の正体への3件のコメント
2017年4月9日 12:22 PM
どんな学問でも仮説の上に論理が構築されるもので環境が変われば仮説も変わるし当然その上に立つ論理も変わるだろう、仮説を絶対的な信仰にする、あるいはそのように装うのは論理厳密性やその背後の権威を前に人を黙らせる効果があるからか。経済学はあらゆる学問の一領域でしかなく経済合理性という単一の価値観や物差で人類の活動を計ろうとするものだろう、多様性の尊重を謳いつつ、実際は生活の差し迫った経済移民に選択肢など無く、選択の多様性も営利活動というごく狭い領域の中でのみの話だろう、経済学の前提に国家が無いのだから国家という枠組みを外す道具としての経済学においては国民意識や相互扶助も否定される、電気ガス水道という生活基盤のインフラや、その先の警察消防軍事サービスも採算の取れるもの以外許容しなくなる、というのが理想の世界なのか、国や政府に対する根強い不信感が背後にあるのだろう、言語の使用目的を征服や支配に置き、知識は他人を圧倒するためだけにあると信じている、行動と目的が同一化しているのか、言語は他人と繋がり関係を将来に渡り維持するためにあるのでは、国家や政府の「仕事」は多岐に渡るので当然多様な価値観が必要になるだろう、それは無駄も多く非効率になりがちだ、評価尺度も企業のように利益に置くことも出来ない、経世済民を如何に評価尺度に置けるのかが問われているのか。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
コメントを残す
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です