From 青木泰樹@京都大学レジリエンス実践ユニット・特任教授
———————————————
【PR】
日本が国連に2億ドル払える理由
財政赤字国のどこにそんな大金が?
TVが放送を自粛する意外な真実とは
http://www.keieikagakupub.com/sp/38DEBT/index_mag.php
———————————————
長らくリフレ派理論を批判してきた私としては、先月の「日銀総括(金融政策の総括的検証)」に触れないわけにはまいりません。
そこで今回は「日銀は何を総括し、これから何をしようとしているのか」についてお話しします。
日銀総括の詳しい内容については、日銀HP内の下記資料を参考にしてください。
http://www.boj.or.jp/mopo/outline/qqe.htm/
総括において日銀は「2%のインフレを目指す」という目標(マト)は変えませんでしたが、達成手段(矢)を変更しました。
主な変更点は、調整手段を「量から金利へ」変えること(イールドカーブ・コントロール)、およびこれまで以上に誇張したコミットメントを発するという「オーバーシュート型コミットメント」の二つです。
今回は、それぞれの手段の内包する矛盾を指摘します。
単純に考えて、政策手段を変更するということは、これまでの手段に効果がなかったということですから、「すいません。間違えました」と総括するところでしょう。
しかし、黒田総裁は立場上そうも言えないので、「これまでの量的緩和およびマイナス金利政策を強化する形で新たな枠組みを導入した」と、両論併記で誤魔化そうとしています。
本来、総括すべきは次の二点でしょう。
先ず、マネタリーベースを250兆円も増やしたにもかかわらずインフレ期待が尻つぼみに低下している現状は、外的要因のせいではなく、量的緩和政策の依拠するリフレ派理論が根本的に間違っていたと認めること。
次に、マイナス金利の導入は、名目金利の低下余地が極めて限られている状況では融資の増加につながらず、逆に金融機関の収益を圧迫させるというマイナス面が大きかったと反省すること、です(その意図が円安誘導にあったとしても)。
おそらく黒田総裁も腹の中ではわかっていると思いますが。
さて、一般の方は日銀総括に出てくるカタカナの専門用語に惑わされ、何を言っているのかさっぱりわからないと思われますので、日銀の根本的認識を一点に絞り、先に提示しておきます(それを知れば、後述する私の説明も理解しやすいと思います)。
日銀は物価目標をどのように達成しようとしているのでしょうか。
それは、実質金利を下げて投資を増やし、景気を好転させ、結果的に物価を引き上げるという効果波及経路を想定しています。
それでは実質金利はどのように決まると考えているのでしょうか。
日銀の念頭にあるのは、フィッシャーの方程式です。
実質金利=名目金利−期待インフレ率 ・・・(1)
フィッシャーの方程式は単なる定義式ですが、ポール・クルーグマンはこの式を右辺から左辺への因果式と捉え、実質金利の決定式とする仮説を唱えました。
リフレ派はこの考え方に全面的に依拠し、ゼロ金利制約(名目金利=0)の下でも、期待(予想)インフレ率を引き上げられれば実質金利は下がると考えました。
そして、日銀が2%のインフレ達成までベースマネーを増加させると宣言し、実際にベースマネーを増やし続ければ、人々に2%のインフレ期待を抱かせることができると考えたのです。それが量的緩和政策。
しかし、見事に失敗(その理由はこれまでお話ししてきたので、ここでは省略)。
3年半経っても、日銀が期待インフレ率と考える「ブレークイーブン・インフレ率(BEI)」は9月末で「0.358%」ですから、2%に遥かに届きません。
量的緩和を続けても期待インフレ率が上がらないので、(1)式の名目金利(=0)を強引に引き下げたのが、今年2月に黒田総裁が導入したマイナス金利政策です。
ここで注意すべきは、マイナス金利の対象は短期金利ということです。
このように、これまでの日銀の考え方は「実質金利を(自然利子率より)下げられれば景気は好転するはずだ」ということで、総括後もその姿勢は変わっておりません(自然利子率の話は別の機会にします)。
もちろん、経済学の教科書と違って、現実には実質金利が下がろうと実物投資は増えないのですが今回はその問題に触れずに、日銀の考え方に沿って説明します。
第一に、総括後に新たに示された枠組みのうち「長短金利操作」について。
具体的には短期金利を「マイナス0.1%」、長期金利(10年物国債金利)を「0%」程度で推移するように操作するというものですから、(1)式で言えば、名目金利の引き下げを介して実質金利の低下を狙っている意図が理解されると思います。
ただし、今回はマイナス金利政策に長期金利の操作が加わりました。
実は、長期金利を加えたことで、日銀が量的緩和政策から実質的に転換を図ったことが見て取れるのです。
すなわち黒田総裁のリフレ派理論との決別です。
一応、これまでの年間80兆円の国債買入れ額は「めど」として残されていますが、それは日銀内のリフレ派である岩田規久男副総裁と原田泰審議委員に対する多少の配慮にすぎません。
「量から金利」への政策転換の意味するのは、量的緩和の縮小に他ならないのです。
量と金利を同時に操作することは不可能なのです。二兎は追えない。
量を決めれば金利を決められず、金利を決めれば量を決められない。
簡単に説明しましょう。
ひとたび毎年純額で80兆円国債を買い取ることを決めると、金利水準に関わらず目標額まで国債を買い取らざるを得ません。
満期まで保有すれば必ず損をするマイナス金利の国債でも、買値以上の価格で満期前に日銀が必ず買ってくれるので、長期国債がマイナスで取引されているのです(まさに投機)。
逆に、長期金利を0%に決めるとどうなるでしょう。
今度は金利水準を維持するために買うことになりますから、買い取る量は不確定になります。
さらに日銀の罪深いところは、目標とする長期金利の変動幅を示していないことです。
日銀の言う「0%程度」の範囲が定かでないのです。
「0%_α」のαを日銀は恣意的に決められることになります。
その範囲に収まっている以上、国債を買い取る必要はなくなるのですから、間違いなく量的緩和は縮小します。
それで長期戦を乗り切ろうとしているのでしょう。
金融政策だけでは総需要不足を埋められず物価も上がりませんから、大胆な財政出動をしない限り、この戦いはエンドレスになる可能性もあります。
短期金利は政策金利(中銀が誘導したい金利水準)であり、短期金利の操作は各国の中央銀行で実施されている代表的な金融政策です。
ちなみに短期金利には上限と下限、すなわち変動幅(それをコリドーと言います)が設定されています。
短期金利とは無担保で一晩カネを借りるときの金利で、市中銀行が中銀からカネを借りる時の金利(ロンバート金利)が上限で、中銀へ預け入れるときの金利(預金ファシリティ金利)が下限を画します。
日銀の場合、上限が補完貸付制度に基づく基準貸付利率(基準割引率)であり、下限が追加の超過準備に対する預金金利(日銀当座預金の付利)で、現在はマイナス0.1ということです。
日銀は、フラット化しつつあるイールドカーブ(利回り曲線)を「短期金利マイナス0.1%」と「長期金利0%」を結んだ線上に乗せたいのでしょう(傾きをシャープ化したい)。
そうすれば超長期の国債利回りは高くなりますから、長期運用を目指す金融機関にとっても歓迎されます。
ただし、日銀が考える「イールドカーブ・コントロール」はかなり難しいと思います。
公園にシーソーがありますね、二人で乗ってギッタンバッタンする遊具です。
真ん中の支点を長期金利とし、片側を短期金利、反対側を超長期金利とします。
今、短期金利がマイナス0.1%として、それを引き下げた時に長期金利は変わらず(政策で抑えこんでいるため)、超長期金利だけ上昇するというのが日銀の想定です。
しかし、「短期金利のマイナス幅が拡大し、長期金利が一定(0%)の時に、なぜ超長期金利が上昇するのか」という疑問に答える理屈を提示しない限り(実際、示していない)、イールドカーブ・コントロールは概念上の遊びにすぎないと思います。
第二に、「オーバーシュート型コミットメント」について。
これまで「安定的に2%」の物価目標を「安定的に2%超」になるまで金融緩和を継続するということですが、表現を多少強めるだけで、どの程度の効果があるのでしょうか。
ここでの文脈では、これは(1)式における期待インフレ率を引き上げることを目的とするものですから、当初の黒田日銀のコミットメント強化策ということでしょう。
一応、日銀の理屈を見ておきましょう。
驚くべきことに、日銀はこれまで期待インフレ率が上昇しなかった主因として、「わが国ではもともと適合的な期待形成の要素が強い」ことを挙げています。
適合的期待(adaptive expectation)とは、過去と現在の平均値から将来を予想するという期待仮説です(経済学では一般に「適応的期待」といいます)。
日本人は、過去と現在のインフレ率を見て、将来のそれを予想する傾向が強いと言っているのです。
しかし、今頃になって、それも総括時に「日本人は適合的な期待形成をする傾向が強い」と言い出すのは、明らかに「おきて破り」ですね。
適合的期待に対して今後の金融政策の動向から将来のインフレ期待を形成することを、「フォワード・ルッキングな期待形成」と言います。
これはまさにリフレ派理論の想定していた期待形成です。
それに基づき、量的緩和とコミットメント戦略をしてきたわけです。
日本人の期待形成過程において、適合的期待とフォワード・ルッキング期待が各々どの適度の比重を占めているかを日銀は言っておりませんが、2%インフレ目標に遥かに及ばない現況(BEIの水準)からすれば、大半の人たちは適合的に期待形成をしていると推察されます。
もしも、そうした日本人の期待形成がわかっていたなら、なぜリフレ派理論に基づく政策を実施してきたのでしょう。
端から、効果が極めて限定的だとわかっていたでしょうに。
適合的に期待を形成する傾向が強いのであれば、インフレ目標の達成のためには現在の物価を上げるしかないのです。
それを可能にするには「積極的な財政出動による総需要の増加策しかあり得ない」のです。
おそらく3年半前の黒田総裁に、「日本人は適合的に期待形成する傾向が強い」という認識はなかったと思われます。
それゆえリフレ派政策を実施した。
しかし、効果が表れないことで一年ほど前からリフレ派理論に対する疑念が生じ、本年2月にマイナス金利政策に転じたころには、リフレ派理論からの離脱を決意していたのでしょう。
ただ日銀総裁としては、これまでの政策の言い訳をする必要があった。
それで総括時に適合的期待を持ち出したのでしょう。
しかし、図らずもこのことが日本における金融政策の限界を示すと同時に、現在の総需要不足解消の必要性、すなわち財政出動の必要性の論拠を期待形成の観点から示すことになったのです。
「2%」を「2%超」と言い換えるオーバーシュート型コミットメントで日本人の期待形成過程を抜本的に変えられるとすれば別ですが、私にはどう考えても無理なような気がします。
ーーー発行者よりーーー
【PR】
いわゆる「国の借金」問題の真相はこちら…
http://www.keieikagakupub.com/sp/38DEBT/index_mag.php

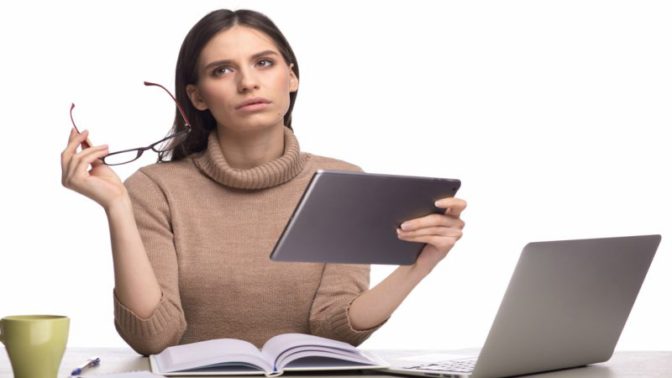
















【青木泰樹】期待はずれの日銀総括への2件のコメント
2016年10月8日 7:28 PM
仰しゃる通りでございます。何度も言いますが、航空力学で例えると、推力が抗力を生み、抗力が浮力を生むのであって、浮力が抗力を生み、抗力が推力を生みません。また浮力を生み出すには抗力を生む推力のパワーがより大きくなければなりません。リフレ派理論のままでは紙飛行機と同じです。一度手から離れた紙飛行機は上昇しますが推力がなくなれば落下に転じます。落下も抗力なので浮力が生まれ再度上昇いたします。しかし残念ながら最初の高さまで上昇することはできません。それを繰り返し最後は墜落してしまいます。上昇気流があれば別ですが。しかしそんな外的要因は計算できませんし当たり前ですが下降気流もあります。推力を生み出すパワーとは『GDP』であります。リフレ派さんが抗力を浮力に変える素晴らしい機体を作ったのならば推力を生むエンジン、そのエンジンを動かす油を大量に注ぐことこそ政府の務めであります。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2016年10月10日 3:16 PM
何よりも守りたいのは「自分達の賢さという地位」だから言い訳にも空虚な用語やカタカナ英語を使わずには居られない。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
コメントを残す
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です