From 青木泰樹@経済学者
———————————————————-
●三橋貴明公式YouTubeチャンネルでは最新動画を続々公開中
https://www.youtube.com/user/mitsuhashipress/videos
———————————————————-
バズーカは砲弾を発射するとき、背後へ猛烈な爆風を噴出します。
それゆえ射手は前方の標的ばかりでなく、後方にも注意を払わねばなりません。
人が居たら大変です。吹き飛ばされてしまいますから。
黒田日銀総裁は、先日、追加の金融緩和策を発表しました。
これまでの資金供給量の目標である「年60〜70兆円増」を10兆円から20兆円積み増やして「年80〜90兆円増」へ、また長期国債の購入額を「年50兆円」から30兆円増やして「年80兆円」にするというのが主内容でした。
日銀が民間へ資金(ベースマネー)を供給する手段は、民間金融機関の保有する債券類を購入する以外にありませんから(日銀特融は除く)、新目標の「年80〜90兆円増」の内訳は「長期国債80兆円分購入+α」ということになります。
ETFの購入量を増やした分、短期国債の購入量を減らすということでしょう(マイナス金利で取引されてましたからね)。
ただし今回の黒田バズーカ第二弾は、第一弾の時と比べるともろ手を挙げて賛同する人は少ないようです。
日銀の政策決定会合でも、民間出身の政策委員4人全員が反対にまわり、「5対4」の薄氷の決定であったそうですし。
経済は生き物と言いますから、経済状況が変われば評価も変わるのは当然のことでしょう。
さて、本日は黒田バズーカの功罪についてお話ししたいと思います。
果たして黒田射手は、バズーカ砲の後方確認を行ったのでしょうか。
もしも、そこに国民生活があれば、発射によって甚大なる被害が生じてしまいます。
先ず罪の方から。
今回の黒田総裁の目的は、明らかに自己保身にあったと考えられます。
総裁就任時にリフレ派の論理に基づき「2年で2%のインフレ達成」を目標に掲げた手前、あまりに目標と乖離した結果に終わると彼自身の評価が低落するばかりでなく、日銀の金融政策自体に疑いの目が向けられることにもなりかねません。
そもそもリフレ派の論理を採用したことが問題だったのではないかと。
総裁の任期は2018年4月まで保証されていますが、早期の失敗はかなりの痛手となるでしょうから、何としてでもインフレにしたいというのが本音でしょう。
しかし、周知のように足元の景気は4月の消費税増税によって低迷し、総務省発表の9月のコアコアCPIは前年同月比で「2.3%」の上昇でした。
2%とされる消費税率上昇分による影響を除けば、「0.3%」の上昇に過ぎません。
同時期のエネルギー価格を含んだコアCPIにしろ3%でしたから、実質的に1%しか上昇していません。
黒田総裁の焦りが手に取るようにわかる数値ですね。
インフレは「継続的な物価上昇」と定義されますから、一回ぽっきりの物価上昇だけではインフレとはいえません。今年だけではだめなのです。
現在の水準から来年も再来年も、2%づつ上昇しなければ目標を達成できないのです。
ところが「期待」に影響を及ぼして物価を上昇させるとするリフレ派の理屈どおりに2%の物価上昇が実現するとは、現実的に見て、とても期待できません。
岩田規久男日銀副総裁に代表されるリフレ派の理屈では、「日銀が2%のインフレになるまで金融緩和を続けると強力にコミットメントすれば、人々の期待は変わる。期待インフレ率が2%になれば、実質金利は低下し投資は増加し、将来消費を先食いすることで現在消費も増える。そうした総需要の増加がさらなるインフレ圧力を生む」ことになっています。
このマネタリズムとケインズ経済学を脈絡なく接合したような奇妙な理屈は、現実経済を考えた場合、どう考えても成り立ちません。
二点だけ指摘しておきましょう。
第一に、実物投資は、フィッシャーの方程式(実質金利=名目金利−期待インフレ率)から導出されるような「金融市場で決定される実質金利(貨幣利子率もしくは市場利子率)」の変動にあまり反応しないのです。
ただし金融投資、特に投機は実質金利の動向(インフレ期待の動向)に敏感に反応します。ですからマネーゲームにはつながります。
新古典派的に言えば、実物投資は「金融市場で決定される実質金利」とは別概念の実物経済における自然利子率に依存することになっているのですが、ここでは現実的観点から話しましょう。
誰にとっても明らかなように、実物投資が行なわれるか否かは、当該プロジェクトが儲かるか否かに掛っています。
すなわち予想収益率が問題なのです。
しかし、現実世界は不確実性の世界です。一寸先は闇。
敢えてそこへ挑むからには(リスクテイクするためには)、その対価が必要ですね。それがリスクプレミアムです。
当然、先が見通せない状況であればあるほど、実物投資に挑む人は高いリスクプレミアムを要求するでしょう。
リスクプレミアムをカバーする予想収益率がどれくらいの水準になるかは景気状況によって異なるでしょうが、内閣府の資料(「日本経済2013−2014」)を見ると実物資産の収益率は2012年で10%くらいでした。
新規投資に際してもその程度は要求するでしょう。
資金調達コストとしての実質金利が多少下落したところで、たとえば1%くらい下落したところで反応薄なのです。
結局、実物投資はマインド(将来予測)に依存しているのです。
ここでの将来予測とは正確には「将来の需要予測(造ったものが幾らでどのくらい売れるか)」のことです。
あまり良い例ではありませんが、最悪の制度設計と言われる「再生可能エネルギー買い取り制度」を想起してください。
雨後の竹の子のように太陽光発電、風力発電、地熱発電の設備が出来上がってきました。
需要が確実に見込めるから、儲かるから多額の実物投資が行なわれたのです。
それが実物投資の論理です。
現況において実物投資を増やすには、将来の需要は見込めるが、不確実性のために民間企業が投資を逡巡している分野に対して政府が背中を押すことです。
政府が先導して需要を創出する必要があるのです。
防災減災をはじめとする広範な国防強化策である国土強靭化計画、医療・介護、環境保護といった分野の伸長と地方再生を連結させる制度設計が政府に求められる所以です。
第二に、現実社会に生きる国民は価値観やそれに基づく行動様式が多様であることです。
この多様性が全員一律の期待形成を前提とするリフレ派の論理を打ち砕くのです。
百歩譲って、国民全員が2%のインフレを予想したとしましょう。
リフレ派は、「将来モノの値段が上がるのだから今買っておこう」と皆が行動すると考えています。
しかし、現実には「将来モノの値段が上がるのだったら、それに備えてカネをためておこう」という人もいるのです。人々の行動様式は多様なのです。
インフレ期待によって消費が増えるか減るかは、他の諸要因(所得の増減や社会不安等)の影響も含めた将来の国民の消費行動にかかっており、それは現段階ではわからないのです。
実際にインフレになってみなければわからないというのが本当のところでしょう。
4月から消費税率が3%アップ(いわば人為的インフレ)になってはじめて、「こんなに上がったのか」と実感し、消費行動を変えた人も多いのではないでしょうか(私もその一人です)。
黒田総裁も薄々、「リフレ派の理屈通りにいかないな」と感じていると思います(決して言葉には出せないでしょうが)。
それで就任以来の物価上昇の原因を考えた。
原因は二つしかない。円安による輸入物価インフレと消費税率アップです。
ところが、これまでのインフレ要因は消失しつつあります。
このところの原油価格の下落は輸入物価インフレの圧力を弱め、また景気指標の悪さから来年度の消費税増税を先送りすべきだとの声も大きくなってきました(もちろん、私も声を大にして「現在も実質賃金デフレは継続中であるから、消費税増税などもってのほか」と主張しています)。
それに危機感を抱いた黒田総裁がとった行動が今回の追加緩和だと思います。
来年も物価を上げなければならない、継続しなければインフレにならないからです。
直接的に円安誘導を図り輸入物価インフレを促進させ、間接的に株価急騰を演出し消費税増税実施のための援護射撃を行ったわけです。
しかし、輸入インフレも消費税増税(人為的インフレ)も国民生活を直撃し疲弊させます。
インフレは低下を続ける実質賃金をさらに落ち込ませることになるでしょう。
またデフレ不況へ逆戻りということにもなりかねません。
それを阻止するために更なる緩和策を採りつづけると、いよいよバブルが現実のものとなるでしょう。
ただし、今回の緩和策のうち長期国債の買い取り量を増加させたことは、財政問題の解決につながりますので、「功」の側面と言えます。
この政策手段は「インフレを起こす」というリフレ派の理屈としては成り立ちませんが、財政再建の立場からすれば有力な手段と言えます。
財政問題とは二重構造になっておりまして、「税収と一般歳出のギャップを如何に埋めるか」という基礎的収支の改善の問題および「大量の国債残高をどう処理するのか」という国債残高の処分問題です。
私が以前から主張しているように、長期国債の買い切り量の増大は、正しく後者の解決策にほかなりません(前者の問題は別の機会に論じます)。
経済学者はほぼ全員、「国債の償還資金は税収から」と考えています。
政府の借金の返済は国民が負担するものだと考えているのです。
そこから次世代負担論も出てくる。
しかし、日銀による長期国債の買い切り策はその通念を覆すのです。
国債買い切り量を増やしても、金利も上がらなければインフレにもならないデフレ状況であれば、民間経済に悪影響はありません。
それゆえ「政府の借金をデフレに負わせる」ことが可能なのです。日銀はその媒介役なのです。
国民が負担する必要はないのです(ただでランチが食べられるのです)。
国債残高のうち日銀保有分が増えれば、その分、民間保有の国債残高は減少します。
程なくして、民間金融機関が「これ以上売りたくない、できれば買いたい」という状況がやってくるでしょう(現に短期国債で生じた事態です。もちろん長期国債はマイナス金利にはなりませんが)。
その時点で国債問題は解決したことになるのです。
同時に、そうした状況下では国民生活に必要な建設国債の発行に文句を言う人たちもいなくなるでしょう。
PS
三橋貴明公式YouTubeチャンネルでは最新動画を続々公開中
https://www.youtube.com/user/mitsuhashipress/videos






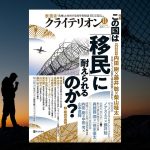










【青木泰樹】黒田バズーカの功罪への8件のコメント
2014年11月8日 3:44 AM
<>リフレ派のモデル構築のための仮定が現実離れしていることが良くわかります。また企業で仕事をしていれば <>まさにずばりで痛快です。金があるかないかの前に儲かる見込みがあれば、借金してでも投資するわけです。同様なことが家計についても言えるのではないでしょうか。本当に価値のある必要なものなら住宅のように借金をしても取得します。 そしてこの逆の命題について深慮する必要があると思います。所得があっても 価値のない物やサ−ビスは買わないということです。とくに高いからこそ買うというバブル期の狂気を体験した現在の日本の家計はそうでしょう。 この視点から見ると現在の総需要不足は単に所得不足や将来の所得への不安にだけ帰せられないと思います。 所得にそれほど不安のない家計も買いたい物やサ−ビオスがないのかも知れません。つまり リフレ派の理論はその誤った仮定の故にほとんどインチキ理論ですが、 たとえば積極財政で企業の投資の後押しをすることによって、景気回復の方向に一時的に動いてもそれだけでは永続的成長軌道には乗らないのではという懸念があります。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2014年11月8日 7:23 AM
社会保障が厚くなったのは、それはそれで富の分配がより公正になって好ましいことですけど、 一方で買えてた人が買えなくなってるわけで国民経済全体の富の産出量は減り続るデフレが続けば最終的には誰もが何も買えなくなるのです。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2014年11月10日 12:07 AM
でも、社会保障は厚くなってきたよ。増税の目的はインフレになるためでは、ないでしょ。今まで、ほとんど買えなかった人が、必要なものを買えるようになったよ。ちゃんと入院費も安くなったよ。消費税は、そのためでしょ。わからないの?
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2014年11月10日 9:58 PM
「国債残高のうち日銀保有分が増えれば、その分、民間保有の国債残高は減少します。」それはその通りですが、政府が借金漬けの状態には何ら変化がありません。 建設国債で一時的に経済が回復しても、膨大な借金の返済に十分な税収増になるとは考え難い。結局問題の先送りにすぎないのではないでしょうか。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2014年11月11日 2:24 PM
日銀による国債買い切りで国債発行残高の問題が解決されるその時に誘発される懸念のある円安や金利上昇の問題が消費税増税により相殺される緩和を続けることによりいつかはバブルが起こる事が想定されるが日銀がETFを購入し続けている事により、その貯えたETFを売り出す可能性を考えるとそれも抑制されるそうこうしているうちに深刻な人手不足により実質賃金も上昇していきメデタシメデタシアベノミクス完璧じゃないすか
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2014年11月12日 7:48 AM
仮説が全て♪経済学の理論といわれているシロモノはすべて仮説(ものがたり)でございませう。どの仮説を採用なさるかはセンスが問われるところかと、、現時点におけるリフレ派の臭さは経済学のケの字もしらないぼくにでも直感で嗅ぎ分けられます。勘の鈍さよ屁の臭さとはよくいわれることですが、、、己の採用する仮説が間違っているのではなく間違っているのは現実の方だと頑に信じて疑わない者を世間では普通バカと申すのでせうか。。。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2014年11月12日 1:16 PM
>「政府の借金をデフレに負わせる」!!!!なんというセンセーショナルな表現でしょう。これを正しく理解できれば、緩和と建設国債だけで日本経済の回復(not成長?)は可能という合意ができるのではないでしょうか?
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2014年11月13日 9:51 AM
政府の借金をデフレに負わせる名言どすわね
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
コメントを残す
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です