From青木泰樹@経済学者 http://keiseiron-kenkyujo.jp/
——————————
●韓国大崩壊 ただ1つの理由
https://www.youtube.com/watch?
——————————
はじめまして。
政治経済の潮流や個別の話題に関して所見を述べたいと思いますの
第二次安倍政権発足後、500日余りがたちました。
本日は、
「経済は生き物である」とよく言われますが、
それゆえ、政治家の宿命が「理想と現実のバランスのとり方」
それが長期的観点に立脚した目的達成のための政治的技法、
特に政治権力に近づきつつも、
しかし、政治家がひとつだけ「ぶれてはならないもの」がある。
それは自らが目指すべき国家観(像)です。
国民を導いてゆく目的地です。
もちろん、目的を達成するための手段、
時には迂回も必要でしょう。
ただ目的地を途中で変えてはならない。
国民を謀ることになる。
それが政治家としての矜持でしょう。
目的地を国民に明示し支持を得て政治家になったならば、
万一、変える場合はその理由を説明し、
さて、
目的地にまっすぐ進んでいるとの確信が、多少揺らぎ始め、
そうした思いを共有する方も多いのではないでしょうか。
橋本政権に端を発し小泉政権で開花した市場原理主義は、
市場メカニズムの完全に機能する場は、
そこで競争するのが効率的だと主流派理論は教えています。
しかし、現実は違います。
現実のリングには、強い人と、中程度の人と、
そこに無差別に競争原理を持ち込めばどうなるか。
結果は明らかでしょう。格差がますます拡がるのです。
それゆえ小泉政権を支えた新自由主義思想は、国民の支持を失い、
当然、この反省を踏まえ、安倍総裁は戦略を練ったはずです。
そこで「デフレ脱却」という経済の旗印と、「
アベノミクスはもっぱら前者に関わるものであり、
この戦略は奏功し政権奪取につながったことは周知のとおりです。
アベノミクス自体は、
いわば溺れかかっている人を助け、船に乗せるようなものです。
これまでのところ、「第一の矢」および「第二の矢」
日本丸の目的地を明示したのが「瑞穂の国の資本主義」です。
安倍総理のこの国家観に、保守層を中心に国民は沸き立ちました。
特に、行き先の全く見えなかった民主党政権後ということもあり、
ここまでは良かった。
しかし、政権発足時から、
しかし、その時点では、
そうした楽観論に水を差す出来事が、消費税増税の決定でした。
なぜ、
財務省の財政均衡主義の呪縛から安倍総理も逃れることができなか
しかし、これは国内問題ですから、対策も打てるし、
日本人の手の中にある限り、まだやりようはあるのです。
しかし、本年1月のダボス会議での安倍総理の演説は、
第三の矢の内容が徹底的な規制緩和策であることを安倍総理自身が
これでは小泉時代への先祖返りです。
それからは、堰を切ったように、
明らかに安倍総理は舵をきりました。
目的地を変えたのです。
トリクルダウン政策の行き着く先は、再びの強欲資本主義です。
それは瑞穂の国の資本主義の真逆の方向です。
この転換の原因は何でしょう。私には、「親米保守」
政治思想に関して門外漢の私は、保守という言葉を字義通り「
保つべきものとは、国家を国家たらしめる伝統・文化・
対するに、その保守に冠される「親米」とは何でしょう。
もちろん、それは情緒的な意味ではなく、
戦後、親米政策によって日本は繁栄してきました。
いわば、親米は国益にかなうものであったことは事実です。
しかし、時代は変わりました。
覇権国家のないGゼロの時代です。
米国の日本を庇護する軍事力は格段に低下しました。
現代において経済関係における親米は国益と対立することになった
親米によって国家の形が崩される事態に至りました。
明らかに親米は保守と対立するのです。
現代において親米保守の立場を堅持することは、
その場合、親米はもはや「追米(米追従)」に他なりません。
国益を棄損することになる。
常識的に言って「国益の範囲内での親米政策」しかないのです。
安倍総理には是非このことを認識していただきたいものです。
ただ、懐疑が失望に変わったとしても、
意気阻喪してはなりません。
その次に備えなければなりません。
私達が日本国民である限り、
戦線が多少後退しても、状況が若干不利になっても、
倦まず弛まず、
PS
経済論理の濫用がわかる名著です。
http://amzn.to/1myklqP
PPS
月刊三橋、最新号のテーマは、「雇用崩壊」。
もし、あなたが外国人労働者受け入れによる、
日本人の雇用と社会の変質を危ぶむなら、、、
https://www.youtube.com/watch?



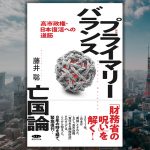












コメントを残す
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です