おっはようございまーす(^_^)/
いまだに日本はグローバリズム真っ盛りですね。
結局、外国人単純労働者を積極的かつ大規模に受け入れることになるようですし、TPPも始まります。米国のトランプ大統領に対抗してか、「自由貿易の旗手」になりたいとか安倍首相は語っています。
(「首相「自由貿易の旗手」へ決意」『共同通信』2018年9月26日配信)
https://this.kiji.is/417483664726803553
しかし、他の先進国をみれば、グローバル化にうんざりしている国は少なくありません。英国や米国は、ブレグジットやトランプ大統領の選出ではっきりしていますし、英国以外の欧州諸国でも、反グローバリズムを打ち出すいわゆるポピュリズム政党が選挙のたびに勢力を伸ばしているところが多いのです。
こうした他の先進国の動向は理解できます。グローバル化のため、先進国では、どこでもこの30年間余りの間に格差が急激に拡大しました。
たとえば、先日の産経新聞の記事によると、現在の米国では、大企業のCEOの給与と社員の平均的賃金の格差は、312対1ということです。1989年は、58対1だったということですので、グローバル化が本格化して以降、ますます格差が拡大していったんですね。
(「ウォール街の高給復活 幹部と社員の格差拡大」『産経新聞』2018年9月11日付)
https://www.sankei.com/economy/news/180911/ecn1809110027-n1.html
それにともなって、庶民の暮らしは不安定化していきました。米国の労働者の平均的賃金は、1970年代半ば以降、伸びていません。例えば、欧州諸国では、子ども一人を生み育てることについても、金銭的なことを考えて躊躇してしまう夫婦が少なくありません。それが少子化の原因の一つだと言われています。
(【施光恒】少子化をめぐる議論の盲点(『表現者criterionメールマガジン』2018年8月31日付)
https://the-criterion.jp/mail-magazine/m20180831/
日本に関していえば、グローバル化が始まった1990年代後半以降、格差が拡大したというよりも、非正規雇用が急激に増え、実質賃金は大幅に下落し、中間層の生活は不安定化しました。多数の普通の人々の暮らしが不安定化し、生活水準が低下したといっていいでしょう。
なのに、なぜいまだに「グローバリズム」を日本ではもてはやすのでしょうか。なぜグローバル化路線を突き進むのでしょうか。
私は、単純ですが無視できない理由の一つとして、名称から受けるイメージの問題があると思います。
「グローバル」(漢字で書けば「地球化」でしょうか)という言葉から受ける印象が、視野が広く、開放的、外交的、前向き、進歩的、リベラルといった印象を与えるからではないでしょうか。
特に、戦後の日本では、「国際社会と仲良くする」ということが一種の金科玉条ですので、「グローバル化」「グローバリズム」「グローバリゼーション」などと言われると、何かすごくすばらしいもののように思えて、反論しにくいのでしょう。
もしグローバル化に反論すれば、「後ろ向き」「鎖国主義者」「孤立主義者」「ナショナリスト」「内向的」「閉じこもりがち」などというレッテル貼りが待っています。
私は、「グローバル化」というのは、曖昧なぼんやりとした言葉で実態をうまくとらえきれていないと感じます。問題が多い「グローバル化」現象であるのに、名称の与える印象から、「なにか良いもの」「追求しなければならないもの」と受け取ってしまう人が多いのではないでしょうか。ですので、もっと端的に、実態をとらえる別の名称が必要なのではないかと思うのです。
では代案をだせ!と言われそうですので私の提案ですが、「グローバリズム」「グローバル化」を、少し長いですが「多国籍企業中心主義」(英語だとMNC-Centrismでしょうか)、「多国籍企業中心主義化」と呼ぶようにするのはどうでしょうか。
このほうが実態を端的に表しています。
いわゆる「グローバル化」(globalization)とは、普通、次のように定義されます。「国境の垣根が低くなり、ヒトやモノ、カネ、サービスの国際的な移動が自由化・活発化すること、もしくはそれを促進しようとする考え方」。
ここで一番重要なのは、カネ(資本)の移動の自由化・活発化です。また、資本を、国境を超えて動かせることになったことにより、多国籍企業の力が、国家よりも強くなってしまったことです。
多国籍企業は、国家を、いわば脅迫し、自らの有利な制度改革を呑ませることができるようになったのです。
たとえば、日本の財界人もよく口にしますが、「法人税率を下げないのだったら、うちの会社は海外に出ていかざるを得ない」などといって、法人税率を下げさせるのです。
あるいは、米国系の多国籍企業が「グローバル化の時代のメガ・コンペティションに打ち勝つために、日本政府は、働き方改革に真剣に取り組まねばならない」とか、「深刻な人手不足を克服するために外国人労働者の受け入れを認めるべきだ」とか、「観光立国をしたいのであれば、カジノを認めよ」などと、日本政府に「改革」を要求するのです。
もし、これらの「改革」が政府に聞き入れられなければ、多国籍企業は「いいですよ、もう日本から出ていくだけですので」とか、「日本にはもう投資しない。シンガポールに投資先を変える!」とか言って、政府に言うことを聞かせようとします。
日本だけでなく、どの国でも一緒ですが、こう言われると政府は、多国籍企業の要求を聞かざるを得ません。企業が流出したり、投資が入ってこなくなったりして、経済が回らなくなるのを恐れるからです。
いわゆる「グローバル化」の実態はこのように、資本の国際的移動が自由化・活発化したことにより、多国籍企業が国よりも強くなり、国を脅し、言うことを聞かせられるようになったことです。
国の意思決定をするのは先進国の場合、民主主義です。したがって別の言い方をすれば、
多国籍企業の力 > 民主主義
となったということもできるでしょう。
その結果、グローバル化が本格化した1990年代以降、ほとんどの国で、それまでの国の仕組みが大きく変えられ、多国籍企業関係者(主に経営者や投資家)に有利な仕組みができあがっていきました。
また、現在、世界の多くの国では、様々な事柄が多国籍企業の利益の観点から評価され、ランク付けされるようになりました。
たとえば、国自体が、「国際競争力」などといったよくわからない指標で測られ、順位付けされるようになりました。多国籍企業がビジネスしやすい環境を作り出すよう各国が競争するようにせっつかれているのです。
多くの国は、なるべくその順位を引き上げようとさらなる「構造改革」に邁進します。
日本国内のさまざまな領域も多国籍企業の観点から評価され、競争を迫られることが増えました。
たとえば、教育の場では、「グローバル人材」養成が叫ばれますが、「グローバル人材」とは、多国籍企業に使い勝手の良い人材にほかなりません。教育機関がいかに「グローバル人材」を作り出すか、つまり多国籍企業にビジネスしやすい環境をいかに提供するかという基準で測られるようになって来たわけです。
そして、多国籍企業の観点から望ましくないと判断されれば、「改革」の対象とみなされるようになります。独自の商習慣、伝統に根差した法律や各種ルールなどです。
日本の場合、日本語という言語まで問題視され、英語化を進めるべきだ!などという話が様々な領域で進んでいます。
このように、事実上、多国籍企業の支配力が非常に強くなったのが、いわゆる「グローバル化」なのです。
「グローバル化」ではなく、「多国籍企業中心主義化」と呼ぶようにしたら、問題がはっきり見えてくるのではないかと思います。
ながながと失礼しますた…
<(_ _)>

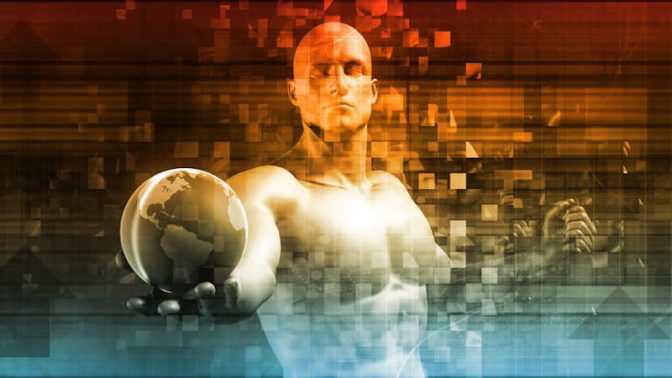
















【施光恒】「多国籍企業中心主義化」と称すべきへの10件のコメント
2018年9月28日 1:44 PM
グローバル
支那では 全球的とか
小生なら 暴力的
グローバル企業=暴力企業
なさってる事は 暴力団と一緒
自由競争と称して 強者が弱者を 死ぬまで打ちのめす
全球的人材=ヤクザの手下
「自由貿易の旗手」になりたいとか、、
三下ごときが 仰るとは 片腹痛し
暴力企業の皆様 拳闘を祈る BOX!!
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2018年9月30日 5:37 PM
グローブ
彼等と同じ globe で勝負したら まいね、、
おらは glove で勝負 だべ ♪
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2018年9月28日 3:16 PM
国際企業主義、というのはいかがでしょうか?
ちょっと短くしてみました。音読も容易かなと。
力点としては、多国籍よりも、企業に置いた観点です。
所詮、一部の人間の損得のための主義なんだ、と。。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2018年9月29日 1:06 PM
確かに最近の人は深く考えることをせず薄っぺらな西洋かぶれで英語的な名前の物を有り難がる傾向がある。特にグローバルと聞けば世界中と言うイメージがありこれに従わなければ自分が世界の趨勢から立ち遅れた人間になるような気がするのだ。そこをグローバル化で一儲けしようとする学者や企業人に付け込まれてまんまとその罠に嵌り気が付けば自分は負け組になって生活苦に苛まれる身分になっているのだ
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
コメントを残す
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です