From 青木泰樹@京都大学レジリエンス実践ユニット・特任教授
国を家計に例えるのはやめよう。
三橋さんも紹介していましたが、9月2日付の日経新聞「大機小機」に掲載されたコラムの表題です。
以前よりこのコラムニストの真っ当な論調に注目しておりましたが、ここまで堂々と財務省の誤りを指摘するとは驚きました。硬骨漢ですね。今後に期待大。
さて、本題に入りましょう。
4~6月の法人企業統計調査によると、企業業績は概ね好調なようです。
経常利益は前年同期比22%強の増加で四半期ベースの最高益を更新し、16年度の「利益剰余金」は前年度より7.5%増え過去最高の406兆円となりました。
ただ利益剰余金を「内部留保」と捉える記事が散見されますが、それは誤りです。
利益剰余金は企業がこれまで積み立ててきた利益の総額を指しますが、全額を現預金で保有しているわけではありません。
それを使って実物資産を取得したり、負債を返済したりしているからです。
残った部分、すなわち利益剰余金のうち現預金で保有されている部分が、いわゆる内部留保といえます。
ちなみに本年3月末の法人預金残高は235兆円で、ここ5年間で60兆円ほど増加しました。問題となるのはこの部分です。
労働需給のひっ迫も報じられております。
7月の完全失業率は2.8%という低水準でした。また同月の有効求人倍率は1.52、正社員のそれに限っては1.01になりました。
俗にいうところの人手不足です。
企業業績が好調で人手不足である反面、厚労省の「毎月勤労統計調査」によると、実質賃金は相変わらずの低迷が続いています。
7月のそれは前年比で▲0.8%でした。
本日は、産業界の活況にもかかわらず実質賃金が低迷する理由について、二つの観点から整理してみます。
先ず、完全失業率の低下と実質賃金の関係について。
失業率の低下は労働市場の需給ひっ迫を意味しますから、経済学の教科書からすると賃金上昇の契機となるはずです。
しかし、現実にそうならないのは、失業率の低下と賃金上昇の相関関係が崩れているためと考えられます。
その原因は経済学の想定しない構造的要因に求められます。
よく指摘されているように、日本の生産年齢人口(15歳以上~65歳未満)は減少が続いております。
この場合、若干の景気動向に関わりなく、たとえゼロ成長下であっても失業率は低下していきます。
例えば、労働意欲のある人が100人いる経済を考えます。現在、そのうちの90人が雇用され、10人が失業しているとします。
分かり易く言えば、90席ある劇場が満席で、外に10人が並んで待っているイメージです。
現在の失業率は「10/(90+10)」ですから、10%になります。
生産年齢の減少とは、この例で言えば、席に座っていた人が外へ出ていき、再度並ぶことはないということです。
今、5人が出ていくとします。すると外の5人が席につく。並んでいる人は残り5人となります。
このときの失業率は「5/(90+5)」ですから、約5.2%へ低下します。そうした状況が継続するのです。
経済成長による失業率の低下とは、ここでは劇場の席が増えることです。すなわち働き手が増えて生産量が増加することです。
例えば、90席が95席になれば、失業率は「5/(95+5)」ですから、5%になります。
これが通常考えられている景気拡大と失業率低下のプロセスです。
しかし、今見たように、労働市場の需給ひっ迫が必ずしも景気拡大(生産増)を伴うものではない場合には、実質賃金への上昇圧力は弱いでしょう。
さらに、退職者を短時間労働者に置き換える場合も、同じく失業率は低下します。
先の例で言えば、8時間労働者1人が出て行った席に、短時間労働者2人が座るとすれば、失業率が低下するのは明らかでしょう。
実際、先の毎月勤労統計調査を見ても、平成27年から常用雇用者は前年比で増えていますが、総実労働時間は逆に前年比で減少している月が多くみられます。
それは短時間労働者への代替が進んでいることの証左です。
以上より、日本固有の構造問題である生産年齢人口の減少が、失業率低下と実質賃金の低迷という状況を両立させていると考えられるのです。
次に、それでは「実質賃金は何によって決まるか」ということを考えてみます。
主流派のミクロ理論は、それに関して明快に答えます。
均衡において実質賃金は労働の限界生産力に一致する、と。
いわば実質賃金は労働生産性によって決まると言っているのです。
ちなみに労働生産性は、「一人当たりの生産量」のことで、Yを実質GDP、Lを労働投入量(就業者数×労働時間)とすると、Y/Lと定義されます。
「造ったものが全て売れる」というセイ法則を前提とする主流派経済学の世界では、労働生産性を決めるのは生産技術だけです。
そのため生産性を上げるには、すなわち実質賃金を上げるには技術進歩に頼る外ありません。
ただこの結論は、供給側の諸要因で実質GDPが先決されているという仮定から導かれたものであることに注意すべきでしょう。
私が以前から主張しているように、GDPが総需要によって決定されるという現実経済を前提とすれば、マクロの生産性に影響を及ぼすのは景気動向(総需要の動向)になるのです。
https://38news.jp/economy/07183
経済学の世界では、実質賃金が労働市場における需給関係によって決定されるのですが、現実はそうはいきません。
経営側が業界平均を参考に恣意的に名目賃金(W)を決めているからです。
実質賃金(w)は、事後的な物価水準(P)の動向を観察して計測されたものです。ここで、w=W/P。
すなわち現実における実質賃金は、労働生産性という物理的条件によって規定されていないのです。
もちろん経営側も労働生産性に無関心ではいられません。
それどころか生産性の高い人材を血眼になって探していることでしょう。
しかし、最終的に賃金を決めるのは経営側ですから、労働生産性の上昇は賃金引き上げの必要条件であっても、十分条件ではありません。
そうした経営側の賃金に関する裁量をマクロ的に示すものが「労働分配率」です。
生産の成果をどれだけ労働者に分配するかというマクロの指標ですが、最適な労働分配率を理論的に導出することはできません。
経済モデルでもそれはパラメーター(所与のものと考えてください)として設定されているだけです。
それゆえ労働分配率の決定には、経営側の裁量が大いに影響すると論じているわけです。
ただし、その裁量の背後にある株主資本主義、ROE至上主義といった経営問題にはここでは触れません。
一般に、労働分配率は、「人件費÷付加価値」と定義されます。
ここで人件費は「1人当たり名目賃金(W)×就業者数(L)」です(今、労働時間を一定にしておきます)。
また名目GDP(P×Y)は付加価値合計ですから、労働分配率は、WL/PY、と表されます。
この経営側の裁量を示す労働分配率と、労働生産性が実質賃金とどのような関係にあるかを簡単に示しておきましょう。
実質賃金の定義式(W/P)から三者の関係を形式的にではありますが、簡単に導出できます。
定義式を少し変形するだけです。
W/P=(W/P)×1=(W/P)×(L/Y)×(Y/L)
=(WL/PY)×(Y/L)
すなわち、実質賃金=労働分配率×労働生産性。
これを変化率の形に書き直すと(対数を取って微分すると)、次の関係が得られます。
実質賃金の変化率=労働分配率の変化率+労働生産性の変化率
もちろん上式は定義式ですから、因果関係を何ら提示するものではありません。
右辺が左辺を決めるのか、逆なのかは何も言えないということです。
今、右辺が左辺を決めるとする仮説を立てるなら、実質賃金の変化率は労働分配率と労働生産性によって決定されることになります。
それでは日本の労働分配率の状況はどうなっているのでしょう。
先の法人企業統計調査によると、平成24年度に72.3%であったのが、その後減少を続け、平成28年度は67.5%となりました。
4~6月の資本金10億円以上の大企業の分配率は43.5%と高度成長期以来46年ぶりの低水準を記録したとの新聞報道もされていました。
明らかに生産の成果に対する勤労者の分配分は相対的に減少しています。
他方、企業業績は好調で、法人の現預金も膨れ上がっていることは冒頭で述べた通りです。
企業収益から勤労者へのカネの流れが滞っていることは一目瞭然でしょう。
ただ、このパイプの詰まりを取り除くことは民間では無理です。
この詰りこそが産業界の裁量の結果だからです。恣意的にそうした仕組みにしているのです。
もちろん労働分配率が今後も低下を続けても、先の仮説を用いれば、労働生産性の向上がそれを上回れば実質賃金は上昇していくはずです。
しかし、これも難しい。
個々の企業における生産性向上は企業努力で可能となるにしても、マクロレベルで生産性を向上させるには経済成長しかないからです。
今、政府は「働き方改革」の柱として脱時間給制度、すなわち労働時間ではなく成果によって賃金を決める制度を導入しようとしています。
以前より、「残業代ゼロ法案」として経団連が導入を求めていた制度です。
政財界は、この制度によって効率的な働き方や生産性の向上につながると主張していますが、ミクロ的にもそれは完全に誤りです。
個別企業の労働生産性を考えてみましょう。それは「Y/L」でした。
脱時間給制度は、「成果(Y)」を経営側が決めて、「労働時間(L)」を勤労者が決める制度です。
言うまでもなく、Yが一定の時、Lが減少すれば生産性は向上しますが、逆にLが増加すれば、生産性は低下するのです。
Yの設定次第で、どちらになるかわからないので、その制度が生産性向上に役立つという論理は誤りなのです。
実質賃金の低迷の原因を探ってきましたが、日本固有の構造的要因および経済界の恣意的な分配方針に突き当たりました。
現状のままでは、実質賃金の上昇を望めません。民間では解決できない問題なのです。
デフレを完全に脱却し、経済成長を成し遂げることでしか実質賃金は上がりません。
その手段は、これまで繰り返し述べているように、継続的な政府による需要創出以外にありません。
長期計画に基づく財政出動が必要な所以です。













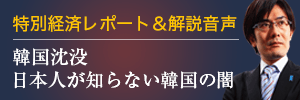
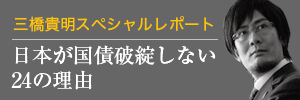



【青木泰樹】実質賃金が低迷する理由への3件のコメント
2017年9月9日 10:35 AM
分かりやすい理屈でした。相対的な理屈を誰かが書くまでは、これを基礎に考えるようにします。
言葉を変えると、政府が最低賃金、最低労働時間を規制し、恣意的に名目賃金を上昇させる事が有効だと言っているんですね。
数字を上げるには、何から何まで政府が労働者階級に有利な政策をしないとだめだと言っているのですね。
労働者階級は全部政府がアホな政策をするからその犠牲になっているのですね。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2017年9月9日 3:39 PM
弱肉強食が推奨される殺し合いの荒野では強者のみが弱者を好き勝手に扱うことを許される。
そこで弱者を守るための組織であったはずの労働組合や協同組合や政府や自治体はこぞって経営者や株主のふりをして強者に味方するようになってしまった。これでは労働者が強大な強者に何ひとつ太刀打ちできずされるがままの無防備状態である。こんな状態で労働者に分配される賃金が自然に上がるわけがない。たとえ人手不足で苦しむ羽目になっても上がらない上げられないが続いて緊縮デフレが完全解消されるまでは難しいでしょう。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
コメントを残す
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です