From 島倉原@セゾン投信
おはようございます。
いつまでも夏気分では風邪を引きそうなくらい、涼しくなってきました。
消費増税の最中、今年はサンマが豊漁なのが、ささやかななぐさめです。
さて、秋といえば読書の秋。
本メルマガでも先週、昨日と取り上げられている中野剛志さんの新著「世界を戦争に導くグローバリズム」、私も読んでみました。
http://amzn.to/1ynsffA
同書は、「理想主義」「現実主義」という国際政治経済学における2つの理論的枠組みを検討しながら、冷戦後のアメリカ外交を分析しています。
そして、「民主主義」という価値の実現を重視する理想主義への傾斜がイラク・アフガン戦争で失敗に終わり、オバマ政権以降は勢力均衡を重視する現実主義に方針転換したこと、こうした方針転換がアメリカのグローバル・パワーの地位からの退位や中国の東アジア覇権を目指す動きにつながっていることを明らかにしています。
他方で、日本では左派のみならず、日米同盟の深化や延命を唱えるばかりの保守派もまた理想主義を共通の基盤としている実態を指摘すると共に、これでは日米外交理念に断層が生じ、中国が将来仕掛けるであろう東アジアでの覇権戦争に巻き込まれた場合に日本の生存と独立の確保が困難になる事態を招きかねないと警鐘を鳴らしています。
その帰結は、戦後欠落していた現実主義的な知識・分析を出発点に据えるべきであるという主張であり、同書の中でもそうした観点から、現在の中東情勢、ロシア・ウクライナ情勢、そして中国の動向についての現実分析が提示されています。
同書によれば、アメリカが理想主義外交に基づく過ちを犯したのは、これがはじめてではありません。
第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけてのいわゆる戦間期にもまた、経済自由主義、今でいうグローバリズムに根差した理想主義外交を行い、その結果醸成されたバブルが世界恐慌を引き起こし、第二次世界大戦につながっていったとされています。
そして、中野さんが同書を書くにあたって出発点としたのが、この戦間期の国際関係を理想主義と現実主義を対比させながら分析している国際政治学の古典である「危機の二十年」です。
「危機の二十年」の著者は、イギリスの歴史家で政治学者のE. H. カー(1892〜1982年)。
第二次世界大戦勃発の数か月前という、きわめてリアルなタイミングで書かれています。
そうした背景にも惹かれ、今回はこちらも合わせて読んでみました。
http://amzn.to/1C7DHKJ
「危機の二十年」の分析の起点となる第一次世界大戦終了時といえば、戦前の日本の株式ブームがクライマックスに達したタイミング。
ちょうど、冷戦終了のタイミング(1989年)がバブル相場のピークであった事実と重なります。
いずれも何やら、歴史の転換点を象徴するような出来事です。
「危機の二十年」では、理想主義と現実主義の内容やルーツを詳細に検討した上で、その目的自体が人間の行動という「分析対象となる事実」に影響を及ぼすことから、ややもすると理想主義に偏りがちな学問として政治学をとらえています。
そして、理想主義と現実主義の双方に基礎づけを求めるのが健全な学問のあり方であると説いています。
このあたりは、「市場経済は均衡状態に収れんする性質を持つ」とする主流派経済学のあり方を批判する、アメリカの著名投資家ジョージ・ソロスの議論(再帰性理論)とも重なります。
http://amzn.to/1hZjQoB
また、「世界を戦争に導くグローバリズム」でも紹介されていますが、「危機の二十年」では理想主義から戦争に至る道を回避する枠組みとして、各国政府が公共事業を拡大することで国内雇用を確保する、という方法に着目しています。
これは、ケインズが国際平和に貢献する積極財政の効用として、かの「一般理論」で説いたことでもあります。
http://amzn.to/1bSpeq8
「危機の二十年」にはこの他にも、政治・経済・社会に関する多面的な切り口からの、現実を踏まえた示唆に富んだ分析が、随所にちりばめられています。
「古典」というととっつきにくいイメージがあるかもしれませんが、同書には「国際関係研究序説」という副題も付されているとおり、当時未だ揺籃期で理想主義的色彩が濃かったであろう国際政治学を具体的な史実に基づき体系化しようという意図があり、(例えば私のように、どちらかといえば経済的分析アプローチを好む人間にとっても)わかりやすくまとめられています。
現在および将来の国際情勢をテーマとしている「世界を戦争に導くグローバリズム」と合わせて読んだことで、より理解が深まったように思います。
ちなみに私自身は、前述した株価の巡り合わせとは別に、「グローバル化進展以降最初に到来した『世界的な超低金利環境=景気循環の一種であるコンドラチェフ循環すなわち長期循環の底』」という共通点から、現在は1900年前後(日本でいえば日清・日露戦争の頃)の状況とも重なっているのではないか、という見立てをしています。
今後そうした仮説を掘り下げていく際にも、両書は恐らく少なからぬ示唆を与えてくれることでしょう。
ところで、現在の日本はどのような方向に進もうとしているのでしょうか。
「世界を戦争に導くグローバリズム」では、安倍政権の理想主義的側面(価値観外交、グローバル化路線、緊縮財政)と現実主義的側面(ロシアとの関係改善意欲)の双方を指摘するにとどめ、あえて断定しない形をとっています。
緊縮財政やグローバル化路線とは、前述した国際平和への貢献とは真逆の効果をもたらすことに加え、(平和的な解決も含めた)現実主義の遂行に不可欠とされるパワー(国力)を自ら削ぐ行為です。
私自身は両書を読み終え、冷戦終結後の現実に対応できないまま理想主義に偏った方向に拍車を掛けているような危うさを、現状に対して覚えました。
また、史実を追ってみれば、具体的な事象こそ違えど、同様な構図は戦間期の日本にもあてはまるように思います。
もちろん、これまで述べたことは私個人の解釈、感想にすぎません。
「本書が描いたのは、その出発点としての分析である。」と「世界を戦争に導くグローバリズム」で述べられているように、両書を通じて異なる現実や時代の変化を読み取ることも可能かもしれません。
http://amzn.to/1ynsffA
http://amzn.to/1C7DHKJ
最後に、そうした問題意識も踏まえつつ、「危機の二十年」の中で印象に残った一節をご紹介して、締めくくりたいと思います。
「バークの有名な言葉に、次のようなものがある。『何らかの変更の手段を欠く国家は、自己の保存のための手段を持たない』。(中略)
こうした見解から、次のような考えが生まれてくるように思われる。すなわち、『侵略』戦争と『防衛』戦争とを道義的に区別しようとするのは間違いだ、ということである。もし変革が必要かつ望ましいものであるなら、現状維持のための実力行使ないし威嚇は、現状を変えるための実力行使ないし威嚇よりも、もっと道義的に責められるべきかもしれない。」(「危機の二十年」、原彬久訳、岩波文庫、393〜394ページ)
↓島倉原のブログ、ホームページはこちら
http://keiseisaimin4096.blog.fc2.com/
http://www.geocities.jp/hajime_shimakura/index.html
↓セゾン投信のホームページはこちら
http://www.saison-am.co.jp/
PS
韓国が絶対に日本人に知られたくないこととは?
https://www.youtube.com/watch?v=ZK5RY5rIGs8












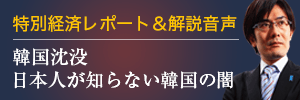
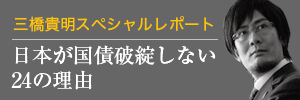



コメントを残す
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です