From 室伏謙一@政策コンサルタント/室伏政策研究室代表
先日、金融審議会の銀行制度等作業部会において、銀行規制を抜本的に見直し、銀行による中小企業への全額出資を可能とすることや、地銀再編の交付金制度の創設を盛り込んだ報告書案が取りまとめられた、というニュースが駆け巡りました。そのニュースではこの実現のための銀行法等の改正案も来年の通常国会に提出される方向であるとされています。
駆け巡ったとは書きましたが、それは我々「界隈」の話で、世間ではほとんど注目されていなかったように思います。しかし、この話、菅政権の中小企業再編政策という名の中小企業淘汰政策と軌を一にする、中小企業をぶっ潰して、地域の雇用を奪い、地域経済を破壊する、日本の技術開発・イノベーションの現場を売り飛ばす、そうしたことにつながるとんでもない話。
是非まずは気づいていただきたいと思い、早速その旨twitterで発信しました。
しかし、更にこの事実を広めていただきたい、地域の中小企業や地銀の方々に伝えていただきたい、そして強い反対の声を、地域から上げていただきたい、そう考え、改めて執筆しています。
ではなぜそうした「とんでもないこと」になりうるかと言えば、まず、出資とは要は株主になることですから、当該中小企業の経営にも、融資の時以上に口を出すようになる、というより経営に参加するようになります。銀行、特に上場している銀行は株主資本主義の虜ですから、短期的な成果を、短期的な数字作りが求められるようになり、そのために「不採算部門」や「低収益部門・事業」の売却や廃止という話にも発展していくでしょう。
彼らにとっては中小企業は、収益を産むための道具でしかない、と言っても過言ではないのです。無論、もう少し長い視点で中小企業に出資して経営に参加するという場合もあるでしょう。その場合も、その目的は企業価値を上げて、最終的には持株を売り払うことが最終的な目的であると言ってしまって構わないでしょう。その場合にあっても、集中と選択の名の下の事業整理や売却、人員整理、つまりは「余剰」とされた従業員の解雇等が行われることになるでしょう。
オーナー社長や長年勤め上げてきた幹部が、腰を据えて、一生懸命働く従業員たちとともに、短期的ではなく長期的な視点で将来の経営の柱とするために研究・開発を続けてきた技術の卵たちも、いとも簡単に投げ捨てられてしまうことになるかもしれませんし、そうなるでしょう。一方で、長年かけて開発された技術や事業は、見ず知らずのファンド等を通じて、それが喉から手が出るほど欲しい海外企業に売り渡されてしまうことになるかもしれません。
更に、銀行とは邦銀に限られるわけではありませんから、日本で銀行の免許を取得した外銀が入ってくれば、もっとえげつないことをしてくることは十二分に考えられます。
「そんな、考えすぎですよ。」なんて思ってはいけません。起きてからでは取り返しがつきません。最悪の事態を想定して、今から行動に移さなければいけません。産業再生機構なるものが何をしたのかを思い出してください。その後「破綻」だなんだと言われた地域の中小企業たちはどうなったのか。




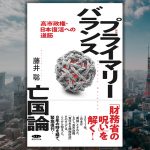












コメントを残す
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です