From 島倉原(しまくら はじめ)@評論家
——————————
<PR>
「日本が国債破綻しない24の理由 ~国の借金問題という<嘘>はなぜ生まれたか?」
http://www.keieikagakupub.com/
p.1_ _日本は「国の借金」でなぜ破綻しないのか?
p.13 ”国民1人当たり817万円の借金”を広める財務省の記者クラブ
p.20 日本国民は債務者ではない、「債権者」である
p.36 かつて、本格的なインフレーションが日本を襲った時代があった
p.42 “日本は公共投資のやり過ぎで国の借金が膨らんだ”は全くの嘘
p.55 グローバリストから財務省まで、消費税増税を訴える人々の思惑
http://www.keieikagakupub.com/
——————————
おはようございます。
本日は前回予告(?)したとおり、マイナス金利政策を取り上げたいと思います。
なお、マイナス金利政策については、先週発表されたGDP統計の論評も含めて詳しく解説した「リフレ派金融政策の破たん」という論稿を別途まとめましたので、後ほどご覧になってみて下さい。
http://keiseisaimin4096.blog.fc2.com/blog-entry-146.html
一言で言って、マイナス金利政策、あるいは過剰な金融緩和は、理論、そして予想される効果の両面において、大きな問題点をはらんでいます。
そもそもマイナス金利政策とは、いみじくも黒田日銀総裁自身も述べているとおり、「お金を借りる、あるいは預かる側がお金の使用料である利息を徴収することはありえない」という常識的な一線、すなわち「金利のゼロ制約」を踏み越えた政策です。
その結果、マイナス金利の日銀当座預金を抱えた民間金融機関が貸出その他の資金運用に駆り立てられ、家計や一般企業の資金調達コストが下がり、経済全体が活性化することを期待しています。
http://www.boj.or.jp/announcements/press/koen_2016/ko160203a.htm/#p0501
ところが、金利のコントロールを手段とするという意味では、実はこの政策、中央銀行の伝統的な金融政策の延長線上に属します。
伝統的な金融政策とは、岩田規久男・現日銀副総裁を筆頭とするリフレ派が20年来、「日銀がマネタリーベース拡大を目標としないことがデフレの原因」「金利を重視するのは時代遅れの『日銀理論』」とレッテルを貼り、散々批判してきたものです。
http://keiseisaimin4096.blog.fc2.com/blog-entry-49.html
つまり、「異次元金融緩和」なるものが思うように効果を発揮しない中で、事実上リフレ派が白旗を掲げたに等しいのが、今回のマイナス金利政策導入なのです。
それを「これまでの中央銀行の歴史の中で、おそらく最も強力な枠組みです」とは・・・。これぞまさしく「リフレ派金融政策の破たん」を示しているばかりか、同稿でも述べたとおり、「盗人猛々しい」とも言うべき状況です。
http://www.boj.or.jp/announcements/press/koen_2016/ko160203a.htm/#p0503
さて、このマイナス金利政策、これまでの金融緩和以上に効果が乏しいというのが常識的かつ論理的な結論です。
実は黒田総裁自身、ご本人にその意識があるかどうかは別として、そのことを事実上認めています。
それは、下記で引用したニュース記事にある「個人預金の金利がマイナスになることは考えられない」という総裁発言を「政策金利をマイナスにしたところで、民間経済レベルでは『金利のゼロ制約』を越えられない」と読み替えてみれば、自ずとご理解いただけるでしょう。
https://twitter.com/sima9ra/status/701242088415858688
そもそも、上記の拙ツイートでも述べているとおり、金融緩和とは本質的に民間金融機関の収益を圧迫する政策なのです。
金利引き下げにせよマネタリーベース拡大にせよ、中央銀行による国債などの購入を通じて達成されます。
ゆえに、そこには「中央銀行が民間金融機関の資金運用競争に参入し、競争圧力を高める」という側面が伴い、いわば資金供給側でのクラウディング・アウトが生じています。
なお、こうした構図が成立するようになったのは、日銀が金融市場を通じたオペレーションを重視するようになった1970年代以降の話です。
「公定歩合」と呼ばれる政策金利に基づく民間金融機関への貸出が、日銀からの資金供給のかなりの部分を占めていた1960年代頃までは、金融緩和は民間金融機関の収益圧迫ではなく、紛れもなくその経営を安定化させる政策であったと言えるでしょう。
現代においても、リーマン・ショックからユーロ危機に至る時期にかけては例外的に日銀貸出の比率が急増し、金融市場の安定化に貢献しました。
というわけで、少なくとも現代では、「不況の時には、効果が乏しい金融緩和もやらないよりはマシ」という議論は、実は大抵の場合成立しないことになります。
なぜなら、経済全体の所得が拡大しない中で民間金融機関の収益を圧迫すれば、彼らの経営が不安定化するか、収益圧迫の分が何らかの形で家計や一般企業に転嫁されるか、いずれにしても経済全体にとってはマイナスだからです。
例えば、マイナス金利を先行して導入しているスイスでは、住宅ローン金利が逆に上昇するという事態が生じています。
また、ある市場関係者から聞いた話なのですが、実はマイナス金利政策導入が決まった直後の日本でも、国債に買いが集中してその金利が低下した反面、企業が発行する社債などは売り圧力が強まり、むしろ金利が上昇したそうです。
http://jp.reuters.com/article/ecb-negative-column-idJPKBN0TL0A720151202?sp=true
すなわち金融緩和とは、経済全体の所得と共に、金融機関の収益も拡大するという前提があってはじめて正当化される政策なのです。
全くと言っていいほど経済成長が実現せず、デフレ不況に苦しんできた1990年代後半以降の日本経済においては、度重なる金融緩和によって、民間経済は全体として圧迫されてきたということになります。
https://twitter.com/sima9ra/status/700718824329318401
http://on.fb.me/1oPwhdQ
その意味では、急激な変化こそ好ましくないとしても、マイナス金利政策はもちろんのこと、異次元金融緩和なるものもできるだけ速やかに解消することこそ、日本経済にとっては本来望ましい政策でしょう。
なお、これは「金融引き締めをすればするほど経済が良くなる」と言っているわけではありませんので、念のため。
バケツが満杯の時には、運べる水の量を増やそうとしてそれ以上水を入れても意味はなく、かえって周りが水浸しになるだけですから、まずは蛇口を止め、さらには水浸しになった周囲の後始末をすべきです。
だからといって、既に入っている水まで捨ててしまう必要は、無論ありません。
日本経済にとって必要なのは言うまでもなく、民間経済の所得拡大をもたらし、新たな投資や消費の意欲を喚起する、財政支出の拡大すなわち積極財政です。
上記の例えをなぞるならば、バケツの数を増やす、あるいはもっと容量の大きなバケツを用意して、周囲にあふれた一部も含め、水をより有効活用する行為にあたります。
積極財政は、金融緩和によって最大の恩恵をこうむっている政府が、しわ寄せを受けた民間部門に対してその果実を還元するという意味でも、筋の通ったまっとうな政策と言えるでしょう。
拙著『積極財政宣言:なぜ、アベノミクスでは豊かになれないのか』でも述べているとおり、過剰な金融緩和に依存したアベノミクスに代わる、積極財政を柱とした新たな政策ビジョンが求められているのです。
http://amzn.to/1HF6UyO
〈『島倉原の経済分析室』より〉
今回の拙稿に対しては、「金融緩和には円安にして輸出を促進する効果があったではないか」という疑問を抱いた方もおられるかもしれません。
それに対して、「円高はそもそも日本の長期不況の原因ではない」というのが上記『積極財政宣言』の回答ですが、それよりは少し短期的な観点から、「2012年以降の円安トレンド自体はグローバル経済のメカニズムによってもたらされたもので、異次元金融緩和は投機的な変動を増幅したものに過ぎない」という回答も存在します。
その論拠に興味を持たれた方は、是非こちら「続・ドル円相場の行方」をご覧ください。
http://keiseisaimin4096.blog.fc2.com/blog-entry-139.html
今週号のタイトルは「株式市場の先行きをどう見るか」です。
以前ご紹介した「岩田日銀副総裁の不吉なジンクス?」が日本株の天井を考察したのに対し、同じく市場の内部要因を踏まえつつ、今回は底値のメドについて考察しています。
併せて是非ご活用ください。
http://keiseisaimin4096.blog.fc2.com/blog-entry-147.html
http://keiseisaimin4096.blog.fc2.com/blog-entry-136.html
先週号のタイトルは「ドイツ銀行株急落の背後にある金融市場の病理」です。
直近のドイツ銀行株急落を引き起こした直接的なメカニズム、ひいてはその背後にある金融システムの問題点について論じると共に、その先に想定される危機のシナリオについて、前例も踏まえつつ考察しています。
http://keiseisaimin4096.blog.fc2.com/blog-entry-145.html
〈その他のお知らせ〉
立ち上げたまま1年ほど放っておいたホームページを、久々に更新してみました。
経済評論とは無縁の柔らかい(?)コンテンツも一部用意しておりますので、是非一度ご覧になってみて下さい。
http://www.geocities.jp/hajime_shimakura/index.html
ブログ/ツイッター/フェイスブックページはこちらです。
http://keiseisaimin4096.blog.fc2.com/
https://twitter.com/sima9ra
https://www.facebook.com/shimakurahajime
ーーー発行者よりーーー
「国の借金が1000兆円を超えた」「一人当たり817万円」
「次世代にツケを払わせるのか」「このままだと日本は破綻する」
きっとあなたはこんなニュースを見たことがあるはずです。
その正体とは、、、
http://www.keieikagakupub.com/
『三橋さんは過激な発言をする人だと思っていましたが…』
By 服部
“私は今年退職をして、世間から離れて行く様に感じていました。
そんな時、月刊三橋をインターネットで見つけ、三橋先生の
ご意見を聞くようになり、世の流れに戻る感じがしました。
月刊三橋を聞き始めて3か月になります。
最初は過激な発言をする人だなあと思って聞いていましたが、
今回の国債破綻しない24の理由を聞いて、
今まで何回も聞いていた内容が、私のように頭の悪い者でも
やっと理解出来るようになりました。有り難うございます。
これからの日本の為にも益々頑張って頂きたいと思います。”
服部さんが、国の借金問題について
理解できた秘密とは・・・▼▼
http://www.keieikagakupub.com/

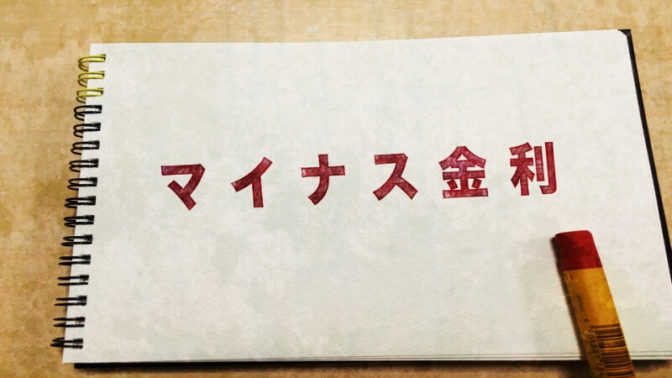
















【島倉原】マイナス金利政策の弊害への1件のコメント
2016年2月25日 6:50 AM
金融政策だけで経済を考える人は時代遅れの帆船論である。帆船とはマストに大きな帆を広げ、風(抗力)を利用し前進(推力)する乗り物であります。これを経済でわかりやすく例えると、以前藤井氏が「ついに暴かれたエコノミストの嘘」で暴いていたように、2002年ごろから2007年ぐらいまで、マネタリーベースの増加(帆)とGDP(推力)の増加が相関関係があるとリフレ派が語っていたのですが、確かにマネタリーベースと言う帆を広げましたが、帆事態に推力はありません。米国バブルと言う追風があったから前に進めたのであり、帆事態に推力があるのならば現時点でGDPが伸びなければ辻褄が合わず、リフレ派が今の現状を「世界情勢の影響だ」と言っている時点で、金融政策(帆)に推力が無い事を認めていると同じ意味になります。また向かい風になれば、帆の操作を間違うと後退するおそれすらあり、嵐だと帆が邪魔をする事すらあるのです。当たり前ですが無風だと停滞いたします。こんな時代遅れの帆船論をやめ、自らの力で推力(財政政策)を作り、それにともなう抗力を揚力(金融政策)に変えることであり、つまり推力が目的であり揚力は手段であることを理解することで安定した飛行、すなわち帆船論ではなく飛行論で経済を考えるべきではないでしょうか。ちなみに、政府エンジンの出力を上げればそれと連動し民間エンジンの出力も上がります。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
コメントを残す
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です