From 青木泰樹@経済学者
————————————————————–
●月刊三橋「イラク危機徹底解説」の申込〆切は8/10まで。
http://www.keieikagakupub.com/sp/CPK_38NEWS_C_D_1980/index_sv2.php
————————————————————–
いわゆる「定義」というものは、議論の出発点となる「取り決め」もしくは「約束事」のことで、いわば相撲の土俵のようなものです。
それゆえ定義を変えれば、土俵が動くわけですから、勝負の行方(結果)も変わってくるのは当然でしょう。
経済関係の統計指標は、言うまでもなく、景況感の判断材料に用いられます。
しかし、経済指標の定義の仕方によって景気判断が間違う危険性があることを、前回、潜在GDPを事例に述べました。
http://www.mitsuhashitakaaki.net/2014/07/12/aoki-4/
本日は、「完全失業率」についてお話しします。
結論から言えば、この指標もまた、「主流派経済学の交替劇」と「経済構造の(人為的!)変化」の結果として、景気判断基準としての役割を減じつつあることです。
さて、完全失業率は「完全失業者_労働力人口」として定義されますが、今回は、この定義自体ではなく、その中身に関して論じます。
すなわち「失業の定義」と「労働力人口(および就業者)の捉え方」について問題点を指摘します。
経済学では主たる失業の定義が二つあります。
先ず、失業を「自発的失業+非自発的失業」と捉えるケインズの定義です。非自発的失業とは「現行賃金で働きたいが仕事がないので失業している」状態のことです。
次に、失業を「摩擦的失業+構造的失業+循環的失業」と考える新古典派「的」定義(主流派の定義)です。
こちらは、失業が景気循環(需要不足)によって生じるか否かを問題にします。ちなみに需要不足による失業が循環的失業です。
さらにマネタリズムでは「摩擦的失業+構造的失業」の部分を「(広義の)構造的失業」と見なし、それを労働力人口で除した値を「自然失業率」と定義しています。
さて、こうした定義からして、ケインズも主流派も不況期における失業を考慮している点では一致しているのではないかと思われるかも知れません。
しかし、それは違います。
実は主流派の失業の定義は、不況を想定しない新古典派の経済観からすると矛盾しているのですが、現実との辻褄合わせのために無理を通しているのです。
理論的に言えば、ケインズの場合は「需要不足=不況」ですが、新古典派では「需要不足=長期均衡からの一時的乖離」なのです。
どこが違うのでしょうか。
個人(主体)が満足しているか否かが違うのです。
ケインズの世界では、非自発的失業者は不満をもって生きています。
しかし、新古典派の世界では不満を持っている人はおりません。
なぜなら、失業者は「職を失ってはいない」からです。
実は、われわれの考える現実的(物理的)な意味での失業者は一人もいないのです。
新古典派における失業とは、「全員が自主的な選択によって、全員一致で何パーセントかの労働供給を減少させている状態」なのです(同質的経済主体を想定しているため)。
そのパーセントが失業率です。
例えば、労働力人口が100人の場合、5%の失業率は現実には5人の失業者を意味しますが、新古典派では全員が就業しているが、とある事情のため自発的に皆5%だけ労働供給量を減らしている状態を意味することになります。
では、なぜそうした均衡からの乖離が起こるのでしょうか。
それは貨幣錯覚のためです。
情報ラグや政府の裁量的行動が原因となって、合理的主体は一時的に貨幣錯覚に陥って行動します。その結果、経済が長期均衡から一時的に乖離するのです。
しかし、その場合も各主体は自分の行動は正しい(合理的)と思っているわけですから、すなわち主体的均衡は保持されているわけですから、不満はないのです。
こうした新古典派の失業観が現実的に荒唐無稽であることは論を俟(ま)ちませんが、現在の主流派経済学は新古典派なので、大半のエコノミストはその論理をベースに現実経済を分析しているのです。
論理と現実を脈絡なく混ぜ合わせているのです。
しかし、水と油ですから混ざりようがない。
分離してしまう代表例が、構造的失業です。
構造的失業とは、「働きたいが、求人要件を満たせないために失業している状態」を指します。
求人側の提示する年齢、資格、性別その他の要件を求職側が満たせない、いわゆるミスマッチ失業です。
ケインズ的に言えば、構造的失業は非自発的失業の範疇に入ります。働く意欲はあるが仕事に就けない状況は両者とも同じだからです。
しかし、新古典派には非自発的失業の概念がありませんから、政府が救済する必要のない自発的失業に分類されてしまいます。
問題は、マネタリズムの意味での構造的失業率が完全雇用と両立する、いわゆる「完全雇用下の失業率(均衡失業率)」となることです。
前回指摘したように、現況の失業率が10%であっても20%であってもその状態が継続すれば、いずれデフレギャップは解消されますから、その水準が「構造的失業率(=自然失業率)」になってしまうのです。
新古典派の論理からすれば、構造的失業は需要不足が原因ではないから放置されることになります。
よくミスマッチ失業に対して職業訓練の必要性を声高に叫ぶ新古典派の御用学者がおりますが、構造的失業を自発的失業に分類している立場からすれば、それが論理的に矛盾していることは明らかでしょう。
「構造的失業率は自然失業率である」との経済観に立脚すれば、結果的に、低空飛行の経済状況が追認され、そこから下降すること(構造失業率の上昇)は許されても、人為的に上昇すること(財政出動)は許されないことになる。
デフレギャップが解消されれば、財政出動の論拠はなくなるからです。
まさに新古典派の論理が生み出す災害です(学災?)。
問題の本質は、職場のIT化と同時に産業の空洞化の進行によって国内における雇用環境が悪化していることです。職場が海外へ流出していることです。
最終的に国内に残るのは、高度な知識や技能の必要な産業および低賃金労働を課される特定のサービス産業だけになりかねません。
とすると、今後ますます構造的失業率は上昇する可能性が高くなります。
新古典派的失業観から脱却しない限り、経済の低空飛行が正当化され、それが続いてしまうのです。
ミスマッチ失業は、就労意欲のある勤労者の遊休化ですから、それこそ人的資源の無駄遣いに他なりません。
政府は、その対策を個人の自己責任に帰すること無く、主体的に国内における雇用の場を創出する必要があるでしょう。政府の責任として。
残念ながら、安倍政権は逆方向を向いているようです。
労働力人口および就業者の捉え方に関しても一言しておきます。
労働力人口は、15歳以上の働く意欲のある人から構成されています。
その際、「正規で働きたい」か「非正規で働きたい」を問われません。
したがって、就業者も正規雇用者と非正規雇用者の合計として定義されます。
周知のとおり、小泉政権時代の「雇用の流動化」策の推進によって、現在の日本は非正規雇用の雇用全体に占める割合が38%強となり(総務省「就業構造基本調査」2013)、年々増加傾向を示しています。
いわば恣意的な雇用規制の緩和によって、経済構造が歪んできたのです。
もちろん、自ら進んで非正規社員になりたい人ばかりであれば問題はありません。
しかし、実態は違うようです。
厚労省の発表によると本年5月の有効求人倍率は「1.09」でしたが、正社員のそれは「0.67」でした。
この数値から読み取れることは、正規社員として採用されなかった人が非正規として就業しているケースがかなりあるということです。
そうした人達は、「正規社員になりたいにもかかわらず、非正規として働かざるを得ない」のですから、ケインズの言葉を援用すれば「非自発的雇用(者)」と言えます。
非自発的雇用は、レントシーカー主導による政府の制度変更によって生み出された社会の不安定化要因です。
同様に、構造的失業率の上昇も、政府が産業の空洞化を放置し、内需主導型の経済運営を怠ってきた結果なのです。
さらに、今後もそうした状況を放置すべしと主流派経済学の理屈は教えるのです。
何をか言わんや。
与野党問わず政治家達の新古典派脳からの脱却(マインドチェンジ)が待たれるところです。
完全失業率は、以前のように国民の暮らし向きを正確に反映できなくなりました。
非正規という雇用形態の出現とその増加によって、職を得ることが生活および所得の安定に直接結びつかなくなったからです。
完全失業率が下がっても、暮らし向きが良くならない状況(実質賃金の低下、雇用者報酬の低迷)が現出しています。
それは非自発的雇用の増加の結果だと思います。
また仕事に就けない構造的失業者の増加も、そうした傾向に拍車をかけています。
現代における雇用情勢の変化に伴い、雇用統計として有用な指標は「完全失業率」よりも「正規社員に対する有効求人倍率」に比重を移すべきだと思われるのです。
PS
前回(7月12日)の寄稿文の中で「総需要が現実GDPを決める」と書きましたところ、「GDPは需要と供給能力のどちらか低い方で決まるのでは」とのご指摘をいただきましたので簡単に補足説明をしておきます。
端的に言えば、供給側で決まるのは潜在GDPです。
しかし、現実GDPは総需要で決まります。
デフレギャップのある時は「総需要<総供給」ですから、自明ですね。
反対に、インフレギャップのある時は「総需要>総供給」となりますから、一見、供給側で決まりそうですが、そうはなりません。供給側で決まるのは潜在GDPだからです。
もしも現実GDPが供給側で決まるとすると、それは潜在GDPに一致することになります。その場合、インフレギャップは発生しません。インフレギャップという概念自体、意味を失います。
したがって、需給ギャップは「総需要で決まる現実GDP」と「潜在GDP(供給能力)」の差として理解するのが適切だと思います。
最大概念を使う場合には、定義上、現実GDPの天井として潜在GDPがあると考えるとよいと思います(現実的には天井を突破することは可能なのですが、生産関数モデルで推計する場合、数式モデルの制約上、需給ギャップが正値をとることはできないのです)。
PPS
中国暴発。三橋貴明の無料Videoを公開中
https://www.youtube.com/watch?v=ns-sXQ-Iey0












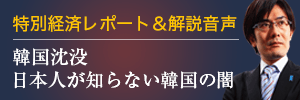
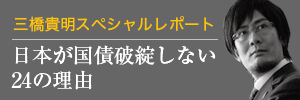



【青木泰樹】完全失業率への3件のコメント
2014年8月9日 9:04 AM
青木先生のミクロ・マクロの教科書があったらわかりやすそうだなぁ
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2014年8月10日 2:09 AM
ほんとうに解りやすい。青木先生は、四角い部屋をまるく掃いて済ますような、雑なことを決して言わないお方だ。しかも、筆致、語り口、こんなに優しいのに、新古典派・詭弁家の神経節を狙った青い光鋩がきょうも鋭く垣間見える。青木兵器先生、と脳内で変換させていただいています。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2014年8月11日 9:24 AM
psの所のGDP概念、判り易過ぎマウスわよ
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
コメントを残す
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です