From 藤井聡@京都大学大学院教授
政府が32兆円の第二次補正予算を決定しましたが、本日はこの件について、以下の三つの論点を指摘しておきたいと思います。
第一に、これでは、全く足りない、ということ。
今の日本経済はコロナショックのみならず、昨年の10月消費増税によって激しく傷付いております。これまでの推計でも、20%を超えるGDP被害があるとも言われており、したがって、100兆円の真水が必須であると同時に、消費税の凍結が不可欠な状況です。
それを踏まえたとき、「消費税を10%に据え置いたまま、真水を32兆円支出するというだけ」では、経済被害を幾分緩和することに貢献することはあっても、経済縮小を食い止める力は全く無いと言わざるを得ません。
第二の論点は、この32兆円の中身を見ますと、しっかりとした執行を目指せば、「32兆円全額真水として活用可能」なものなのですが、逆に「予算執行をしないでおこう」とすれば、わずか10兆円しか真水が出ない、という中身になっている、という点。
そもそもこの32兆円は大きくわけて3つのパートに分かれています。
第一パートは、いわゆる通常の「真水」。これは、適正に執行されれば、日本国内のマーケットに注入されます。
第二パートが約12兆円の「企業の資金繰り支援」。これは、融資、投資の部類で、「貸し付け」分に相当します。したがってこれを通常に運用すれば、単に貸し付けるだけで「後で返せ」という話しになり、結局資金が注入されたことにはなりません。
しかも、これから貸し付け業務をしっかりやらなければ、ほとんど貸し付けることなく終わってしまうことも可能です。
ただし逆に、この枠を使って精一杯貸し付け、そして、すべて「劣後ローン」という返済を必ずしも強要しないタイプの貸し付けで行うことができれば、そして、その資金がすべて「赤字企業」に貸し付けることができれば、実質上この12兆円は「真水」として機能します。
なぜなら、赤字企業が劣後ローンを借りても、十分な黒字が将来出ない限り、返済義務はないという格好になるからです(それが、劣後ローンと呼ばれるものの特徴なのです)。
つまり少々複雑ですが、この12兆円の「資金繰り支援」は適切に運用すれば、「真水12兆円」として実質上機能するものなのです。が、不適切に運用すれば「真水0円」にしかならないというものなのです。
最後の第三パートは「予備費」で、これも10兆円です。
これについては、支出項目が確定していないもので、これから柔軟な判断に基づいて支出していくものです。
この点について、例えば今朝の日経新聞で、慶応大学経済学部の土居教授は、予備費については、財政再建の視点から「使い切るな」という恐るべき主張を論じておいでです。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO59664630X20C20A5EE8000/
無論これは、財務省の見解そのものでありますが、この見解通りに予備費の執行が決定されれば、最悪「0円」という事になります。
以上を踏まえると、予備費と資金繰り支援のための合計22兆円の予算は、真水として積極的に活用すれば「真水22兆円」になるのですが、徹底的に緊縮の態度をとれば「真水0円」となってしまうのです!
ですから、この予算が組めたからといって、32兆円が国民に行き渡るのだと楽観できる状況では全くないのです。
これは、いわば、財務省が仕掛けた罠。
ここで我々が手を緩めると、32兆円と見せかけて、実際は10兆円程度の真水で済ませてしまうことができる、という「仕掛け」を、優秀な財務官僚達はこの予算の中に埋め込んだわけです。
したがって、この予算枠をつかって国民経済を守り切るためには、まだまだ我々国民はしっかりと政府を監視し、国民経済を救うために給付、補償せよと、声をあげ続けねばなりません。
そして、第三の点は、そんな「国民の声」が無意味なのか意味があるのかという点についてのポイントなのですが、この32兆円の補正予算が決定されたという事実は、政府支出は国民経済救済を求める国民の声によって拡大しうる、という可能性を意味しています。
この件についての安藤裕先生と対談の中でもお話しさし上げましたが、そもそも、一次補正予算が決定された直後は、財務省は二次補正予算を今国会中に議論することは絶対にない、という頑なな態度をとっており、与党幹部達も皆、そのような認識をもっていたのです。
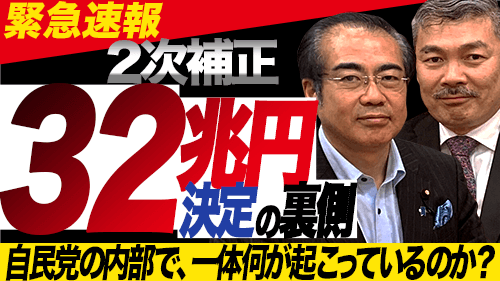
https://youtu.be/NcK8Z5fg4_w
しかしそれでは日本経済が救われることは万に一つも無いということで、政府支出をなんとか拡大すべしという流れを作るため、「日本の未来を考える勉強会」の安藤裕自民党衆議院議員をはじめとした先生方が与党内で様々な議論を重ね、その議論が、岸田政調会長を動かし、それを通して、西村経済再生担当大臣、そして安倍総理による第二次補正予算の決定へと繋がっていったのです。
その間に、国民世論、とりわけインターネットにおいて積極財政を求める声がなければ、こうした流れは絶対に出来なかったのです。
この点については、今後綿密な社会調査を展開していく必要がありますが、政府要人達がインターネットのコメントやハッシュタグなどを極めて敏感に意識している様子は、検事長の任期に拘わる法改正問題においてもはっきりと示されているところです。
その意味において、この(最大で)32兆円の真水は、国民世論と財務省との財政を巡る闘争において、国民世論、特にインターネット世論が「勝ち取った」ものであるとも言えるわけです。
・・・
以上、指摘した三点を改めてここで記載しておきたいと思います。
第一に、32兆円だけでは全然足らない、
第二に、しかも、これからの予算執行で気を緩めれば、真水執行は10兆円に収まってしまう、
第三に、したがって、今後こうした不十分な財政政策を拡大していくことが必要だが、そのためには、国民世論、ひいては「インターネット」上で高めていくことが極めて効果的なのだ、ということが、今回の顛末から明らかとなった。
・・・
以上を踏まえると、読者各位には引き続き、現在の政府支出はまだまだ不十分で有り、かつ、「遅すぎる」という点をしっかりと主張していただきつつ、
#真水で100兆円
#消費税ゼロ
に向けてさらなる世論の盛り上げりにご貢献頂きたいと思います!
そして、そうした世論、そしてインターネット上の盛り上がりは、上記の第三番目のポイントで明らかになったように、確実に政府を動かし売る力を持つのです。
今後とも引き続きよろしくお願いします。
追申:
そもそも、こうした「巨大経済被害」を導いたのは「8割自粛」要請を二ヶ月近くも継続させたことが原因なのですが、前半一ヶ月は致し方ないとしても、後半一ヶ月(GW空け以降)については、科学的データに基づいてもっと早く解除する可能性を探ることが可能であった疑義が濃密にあります。この点には「科学者倫理」上の深刻な問題があると、当方は考えています。是非、下記ご一読下さい。
『公共政策とりわけ感染症対策においては「科学者倫理」の確保が極めて重要である ~尾身氏・西浦氏ら専門家会議の倫理問題を考える~』
https://foomii.com/00178/2020052301264166737


















【藤井聡】「インターネットの力」で、政府支出が数十兆円単位で拡大していく可能性があります。への6件のコメント
2020年5月28日 3:19 PM
いつも的外れな感で、皆様には大変不快な思いかと自覚しておりますが、わたくしから、すれば役所のトップである財務省から全ての機関と政治家さらには有権者に携わる方々の貧困化こそが、日本社会を貧困スパイラルにさせている大きな要因だと思います!取り分け役人と政治家の劣化貧困こそ致命傷と認識しているからこそオールドメディアを過剰に非難しているわけです。それからスーパーシティ法案も可決しなければならないほど国内が逼迫している状況ならば、女性活躍とか子供食堂なども、返って迷惑だと考えるこの頃です。しかし、藤井先生とお仲間の行動に励まされて、なんとか日本を喚起して参りたいと思っております。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2020年5月28日 3:43 PM
適切に運営されなければ32兆円にならないのであれば、動画サムネイルの32兆円決定は不適切ですよね…
自民党の安藤議員と共に内部から変えていこうとするような奇策が
いよいよ歪を帯びているのではないでしょうか?
9月入学にしろ種苗法改正にしろスーパーシティ法案にしろ自公政策はほぼ奇策なので、国民は奇策疲れや奇策不信になってると思いませんか?
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2020年5月28日 8:50 PM
藤井先生らのお話によれば、ツイッター上でのハッシュタグ等を自民党幹部の方々は敏感に見ておられるとのこと。
フェイスブックはやっていても、ツイッターはやっていない方は多くいるように思います。(かくいう自分もそうでした)
しかし、ツイッターは【発信するツール】としては極めて有用なようです。
登録されていない方は是非、思い切ってアカウントを作って情報発信されてはいかがでしょうか?
その際は、
#真水で100兆円
#消費税ゼロ
等のハッシュタグをつけるのも忘れずに。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2020年5月29日 7:36 AM
そもそも藤井教授は3月20日頃に政府が「大規模イベントなどの自粛」「学校の休校」を要請した際に、新型コロナウイルスなどただの風邪に過ぎないのだから大騒ぎする方がおかしいのだ、みんな感染して免疫をつける以外に解決策はない、ウイルスを世界から絶滅させることなどできないのだから仮に自粛で日本からウイルスがなくなったとしても、いずれ外国からまた入ってきて感染者が出る、そうしたらまた自粛を始めるのかと、自粛そのものを目の敵にし、経済を止める方の犠牲者がはるかに大きくなると「予言」していました。
現在藤井教授は盛んに、政府のコロナ対策は完全に間違っていたとか、緊急事態宣言も、自粛すら必要なかったと主張されています。
藤井教授は3月の下旬に感染者発生のピークが来ているのだから、4月16日の緊急事態宣言は無意味だったと主張されていますが、意図的に3月20日頃の自粛要請の効果を無視しているようにしか私には思えません。
国民が新型コロナウイルスによる疾病の被害がどんなものになるか全く分からず、不安になっている時期に政府から「自粛要請」が出たのだから、重大な事態だと感じて当然だと思えます。
とにかく自分が感染しないことに最大の関心があるのは当然として、家族に対し子供に対し社会に対し、自分が感染源になるかもしれないという恐怖もあったはずです。
政府の「自粛要請」に国民が何の反応もせずに日常生活をそのまま続けていたのなら別ですが、現実には「自粛要請」の効果はあったはずと思います。
だから感染者が3月下旬に減り始めたと考えられるのです。
藤井教授はこの部分を意図的に無視して「緊急事態宣言は無意味だった」と言っているようにしか思えないのです。
緊急事態宣言は後追いであっても、感染者が再び増え始めるのを防止するのに役立ったと思えるのですが、この効果も意図的に無視しているようにしか思えません。
重症化や死亡は高齢者や疾患を持っている人がほとんどである
何が主因かわからないが日本は外国に比べて圧倒的に感染者も死者も少ない
こういったことは結果としてわかったことで、あらかじめわかっていたのなら藤井教授は超能力者だということになります。
中国から発表されたデータから予測ができたとしても、中国のデータをそのまま信じることの危険性もあったはずです。
中国や諸外国がどうであろうが、日本で全く同じになるとも限らないし、日本がもっとひどくなる可能性もある。
アジア人は今回のコロナウイルスへの耐性が強かったらしいことがわかってきているようですが、全く逆に、アジア人の方が重篤化する可能性も考慮すべきはずです。
そういったことはあらかじめわからないから。
危機管理の要諦として、まずはできる限り最大限の対策をして、経過を見ながら徐々に緩めていくのが原則だと、素人の私でも知っています。
だから武漢で肺炎が大量発生して、中国政府が武漢封鎖をしているのに、安倍総理が「中国の皆さん観光へいらっしゃい」とやり続けていることが批判されたし、どうして中国からの入国を止めないのだ、習近平国家主席国賓来日やオリンピックの開催の方が国民の犠牲より大事なのかと批判されていた。
どうして早く緊急事態宣言しないのだとも言われていた。
藤井教授のおっしゃり方は、元からの自分の主張と、あとからわかったことをごちゃ混ぜにして、なおかつ都合の悪いことは意図的に無視して、「ぼくの言ったことは正しかったろう」と言いたいようにしか思えないのです。
「どこかの大学教授がラジオで、コロナウイルスってただの風邪だから大したことないって言ってたよ、学校休校なんかとんでもないって言ってたよ、だから気にしなくていいよね」という口コミが広がって、感染者を増やした可能性もある、もっと露骨に言えば重傷者や死者を増やした可能性もあると思っていますが、藤井教授はこの点をどうお考えなのでしょうか。
もちろん因果関係など証明できませんが。
もし自粛も緊急事態宣言も効果がなかったのなら、経済を止めたことによる損失を政府が補償するのは「国家予算の無駄遣い」になります。
政府への要求は、「国民に無駄な経済損失をさせたのだから、政府としては余計な出費になるがその分を補償して罪滅ぼししろ」になるはずです。
これは、自粛や緊急事態宣言に効果があったと感じていて、なおかつ政府への補償を要求している人々とは異なる言い方です。
「政府が自粛を要請するのならその補償もせよ」は、大規模イベントの自粛要請の時からすでに言われていたことです。
政府は金銭的補償をしたくないから「自粛」と言ってるんだろうと批判されていました。
これには「自粛」という経済活動の抑制はやむを得ないものだという前提があります。
藤井教授は「自粛なんかやめろ、普段通りに生活しろ、感染したってさせたってたいしたことはない、自分が無駄に損するだけだぞ、自殺に追い込まれるぞ、政府の言うことなど聞く必要はない」と叫ぶべきだったと思いますが、そうしなかったのはなぜでしょうか。
野放図に蔓延させたら重篤者や死亡者も増えるに決まっているし、医療崩壊も起こるとわかっていたからでしょう。
それと辻褄を合わせるために、藤井教授は「高齢者や疾患持ちでリスクが大きい人への感染の徹底防止」と言い始めたのだと私は考えています。
一人暮らしの老人や疾患持ちはどうすればいいのか、認知症の人は、在宅介護の人は、家族がいるにしても接触をどうしたら避けられるのか、老人や疾患持ちみんなに防護服でも着せるのか。
他の人に蔓延している状態で「高齢者や疾患持ちでリスクが大きい人への感染の徹底防止」といっても容易ではないことは素人にもすぐわかります。
無論すでにわかったことを今後の対策に生かすべきなのは当然です。
しかし藤井教授のおっしゃり方は、ただただ安倍や小池のすることはみんな間違いだ、結果がそれを証明しているだろうというものに聞こえるのです。
すでにわかっていたことと後からわかったことをごちゃ混ぜにして間違いだと批判するのは、相手に予知能力や千里眼のような超能力を求めているようなものだからです。
消費増税の悪影響や「自粛」による経済損失を財政出動によって補償しろというのには大賛成で、この点については政府や財務省が国民をごまかしているし、国民もまた騙されていると思います。
しかしこれは「あらかじめわかっていたこと」の範疇です。
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2020年5月29日 6:27 PM
いつも一般のマスコミで知ることができない情報を配信していただき、ありがとうございます。
さて、27日に、特別家賃支援給付金が発表されました。
この給付金が発表があった当初、思い切った支援だなと思いました。
しかし、27日、蓋を開けてみたら、緊急事態宣言が出された4月からの売り上げが対象になっていないのには、正直、驚きました。
これは、少しでも支援の数を減らそうという思惑があるからでしょうか?
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
2020年5月30日 5:14 PM
[…] とについては藤井聡さんも指摘してはりました(「インターネットの力」で、政府支出が数十兆円単位で拡大していく可能性があります。)。藤井さんは、第二次補正予算案の内容をチ […]
コメントに返信する
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です
コメントを残す
メールアドレスが公開されることはありません。
* が付いている欄は必須項目です